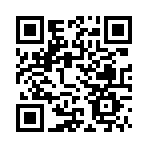2006年09月05日
7、8月の不振は運賃値上げの影響が大きいと見られる
7、8月の観光客数が不振だった理由は、「値上げ」が主な要因であるようだ。
7月上旬の大幅な前年割れ(11.7%減)は、割引の適用がなかったことと、オイル高による運賃値上げによるものと思われる。
8月上旬も3.2%減の前年割れとなり、中旬盛り返したが、結局前年並みに落ち着くものと見られる。
4月以降、航空各社は燃料の高騰により、東京=那覇の場合、片道1300円値上げ、通常期で片道3万6100円などとなっていた。割合からすると3.7%の値上げとなる。割引運賃に占める値上げ率はもっと大きくなるだろう。それに加え、旅行社への卸売価格、割引運賃設定日や席数を減らすなどして、有力旅行社によると旅行商品価格は1割前後の値上げになったという。
オイル価格の高止まりは県内ホテルのコストアップにつながり、最新の自家発電施設を導入した西海岸リゾートが、重油など石油製品の価格高騰で次々に自家発電よりも安くなった電力会社に乗り換えたが、一部、乗り遅れたところがある。(ドッと大手ホテルが乗り換えると送電線の容量不足で電力会社が対応できない)
また、ガソリン価格の高騰は燃料満タン返しのレンタカーの利用料の上昇となる。わたしの感覚ではガソリンは軽自動車で2000円入れて、1週間持っていたのが持たなくなり、一回の給油あたり500円以上値上がりしたように感じている。食材などの配送コストが上がっているはずで、もし値上げできないなら卸売業者の利益が減っていることになる。
さまざまな分野でコストが上昇し、旅行商品価格も上がっている。結果として、観光客は3月まで年間4%増の勢いが予想されたのに、1〜8月まで1.5%増前後の低い伸びとなりそうだ。航空各社の上半期決算がでたあとでちゃんと計算してみるが、1%の運賃値上げで1%程度の旅客減となりそうだ。
ちなみに沖縄銀行の「おきぎん調査月報」8月号は、石油製品価格高騰の影響」を試算している。3年前に比べて石油製品の価格が約40%上がっているが、産業連関表を使って試算した。それによると、
石油製品(ガソリン等)価格の40%上昇が県内物価(生産者価格ベース)へどのようなインパクトを与えるのか試算すると‥‥県内物価を全体で2.59%押し上げることになります。‥‥全国では1.32%押し上げることになります。このように、本県と全国の試算結果を比べてみると、本県の方が各産業に対する全体の価格上昇率が高くなっており(略)
としている。ガソリンが急に40%価格が上がったわけではないが、関連産業がこれまで商品価格を値上げせずに我慢してきたとすると、そろそろ我慢の限界かも知れない。
旅行商品の1割上昇はあり得ないことではない。この価格上昇は、需要が多くて、生産が間に合わずに価格が上がるという物価上昇ではなく、景気は悪いのに価格は上げざるを得ないというもので、ますます需要を減退させ、景気を悪くするものだ。
7月上旬の大幅な前年割れ(11.7%減)は、割引の適用がなかったことと、オイル高による運賃値上げによるものと思われる。
8月上旬も3.2%減の前年割れとなり、中旬盛り返したが、結局前年並みに落ち着くものと見られる。
4月以降、航空各社は燃料の高騰により、東京=那覇の場合、片道1300円値上げ、通常期で片道3万6100円などとなっていた。割合からすると3.7%の値上げとなる。割引運賃に占める値上げ率はもっと大きくなるだろう。それに加え、旅行社への卸売価格、割引運賃設定日や席数を減らすなどして、有力旅行社によると旅行商品価格は1割前後の値上げになったという。
オイル価格の高止まりは県内ホテルのコストアップにつながり、最新の自家発電施設を導入した西海岸リゾートが、重油など石油製品の価格高騰で次々に自家発電よりも安くなった電力会社に乗り換えたが、一部、乗り遅れたところがある。(ドッと大手ホテルが乗り換えると送電線の容量不足で電力会社が対応できない)
また、ガソリン価格の高騰は燃料満タン返しのレンタカーの利用料の上昇となる。わたしの感覚ではガソリンは軽自動車で2000円入れて、1週間持っていたのが持たなくなり、一回の給油あたり500円以上値上がりしたように感じている。食材などの配送コストが上がっているはずで、もし値上げできないなら卸売業者の利益が減っていることになる。
さまざまな分野でコストが上昇し、旅行商品価格も上がっている。結果として、観光客は3月まで年間4%増の勢いが予想されたのに、1〜8月まで1.5%増前後の低い伸びとなりそうだ。航空各社の上半期決算がでたあとでちゃんと計算してみるが、1%の運賃値上げで1%程度の旅客減となりそうだ。
ちなみに沖縄銀行の「おきぎん調査月報」8月号は、石油製品価格高騰の影響」を試算している。3年前に比べて石油製品の価格が約40%上がっているが、産業連関表を使って試算した。それによると、
石油製品(ガソリン等)価格の40%上昇が県内物価(生産者価格ベース)へどのようなインパクトを与えるのか試算すると‥‥県内物価を全体で2.59%押し上げることになります。‥‥全国では1.32%押し上げることになります。このように、本県と全国の試算結果を比べてみると、本県の方が各産業に対する全体の価格上昇率が高くなっており(略)
としている。ガソリンが急に40%価格が上がったわけではないが、関連産業がこれまで商品価格を値上げせずに我慢してきたとすると、そろそろ我慢の限界かも知れない。
旅行商品の1割上昇はあり得ないことではない。この価格上昇は、需要が多くて、生産が間に合わずに価格が上がるという物価上昇ではなく、景気は悪いのに価格は上げざるを得ないというもので、ますます需要を減退させ、景気を悪くするものだ。
Posted by 渡久地明 at 23:27│Comments(0)
│沖縄観光の近況