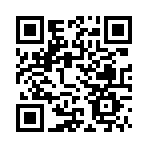2006年10月01日
企業のための大学とは
「会社が新人をとらなくなった。下請けやパート・アルバイトを多用している。会社の技術力は維持できず、あと2、30年経ったら日本は滅びるんでないか」
「大学卒業生が即戦力を要求され、研究よりスキルを優先しろといわれる」
「新人を社内で教育するプロセスがなくなった」
全然業種の違う人たちからたまたま今日、同じ話しを聞いた。
最初の発言は大学の同期。県外のZ君。会社を辞めて、少し考える。その間のカネはあるという。いろんなことを考える年代だとは思うが、会社人間とばかり思っていたのが、とりあえず会社を辞めるという。
聞いてみたら、日本の製造業の現場がおかしくなっているというのだ。社員数千人の会社なので沖縄でいえば巨大企業だが、会社に全然余裕がなくなってきた。どうも社員の戦力強化よりも、つじつま合わせのマンパワー補給が中心となった。2番目、3番目の発言とまったく同じだが、新人教育は会社ではほとんど行わず、安く、即戦力となる人材ばかり補給している。
2番目の発言は県内の大学関係者。学生を送り出す側がZ君の話とよく合う。
わたしが学生の頃は「大学の勉強は会社では全然役に立たない。本当のものづくりは会社が教育する。7年かけてやっと一人前になる」といわれたものだが、いまや企業側が7年もかけて会社の技術を新人に伝えるというプロセスが無駄な時間だと思われるようになり、大学が即戦力の提供を求められている。求めているのは文部科学省であり、企業側だということのようだ。
「それはおかしいと思う。それだと明治以降、戦前の天皇のための大学と同じではないか。天皇のための大学から企業のための大学になったのか。学問のために大学はあるとばかり思っていたが」と問うと、「非常に苦しいところだ。学問をやりながらスキルも教えていると抵抗するのがやっとだ」「会社が時間をかけて新人を教育していたのは10年くらい前までのことで、最近はそうなっていない」とのことである。
3番目の発言は又聞きだが、県内新聞社の新人教育体制だ。これは実際にわたしも日常顔を合わせている連中のことなので、手に取るように分かる。確かに新人教育のプロセスがなくなっているようだ。昔は警察を振り出しに、政治・経済・社会・地方といろんな部門を担当させて、適正の良いところに配置したのだが、いまはいきなり新人が経済部に配置され、企業側が発表するとおりの経済面記事を書いている。社内教育はゼロのようだ。
「基本的なことなんですがー」としょっちゅう携帯電話に電話がかかるけどどうなっているのと、無関係のわたしが県の部長から問い合わせを受けたこともある。どうも人脈維持のためのご機嫌伺いというのではなさそうで、本気で基本的なことを質問しているようなのだ。それだと社内にいくらでも専門家がいるはずなのに、と思う。仕方がないので「部長が好きなんじゃないですか」といってある。
製造業、学生を送り出す方の大学、文系の新聞社とそれぞれに本来の人材教育をだれかに押し付け、押し付けられているように見える。
「あと、2、30年もしたら日本は滅びるんでないかい」
Z君はかなり落ち着いて30年先の話をしているが、世界を不幸にしたグローバリズムをいまさら構造改革といって取り入れ、すでに日本は半分滅びているのではないかとわたしは思っているほどなのだが。
それをひっくり返す強力な抵抗勢力がいまはホントに必要であると思う。
「大学卒業生が即戦力を要求され、研究よりスキルを優先しろといわれる」
「新人を社内で教育するプロセスがなくなった」
全然業種の違う人たちからたまたま今日、同じ話しを聞いた。
最初の発言は大学の同期。県外のZ君。会社を辞めて、少し考える。その間のカネはあるという。いろんなことを考える年代だとは思うが、会社人間とばかり思っていたのが、とりあえず会社を辞めるという。
聞いてみたら、日本の製造業の現場がおかしくなっているというのだ。社員数千人の会社なので沖縄でいえば巨大企業だが、会社に全然余裕がなくなってきた。どうも社員の戦力強化よりも、つじつま合わせのマンパワー補給が中心となった。2番目、3番目の発言とまったく同じだが、新人教育は会社ではほとんど行わず、安く、即戦力となる人材ばかり補給している。
2番目の発言は県内の大学関係者。学生を送り出す側がZ君の話とよく合う。
わたしが学生の頃は「大学の勉強は会社では全然役に立たない。本当のものづくりは会社が教育する。7年かけてやっと一人前になる」といわれたものだが、いまや企業側が7年もかけて会社の技術を新人に伝えるというプロセスが無駄な時間だと思われるようになり、大学が即戦力の提供を求められている。求めているのは文部科学省であり、企業側だということのようだ。
「それはおかしいと思う。それだと明治以降、戦前の天皇のための大学と同じではないか。天皇のための大学から企業のための大学になったのか。学問のために大学はあるとばかり思っていたが」と問うと、「非常に苦しいところだ。学問をやりながらスキルも教えていると抵抗するのがやっとだ」「会社が時間をかけて新人を教育していたのは10年くらい前までのことで、最近はそうなっていない」とのことである。
3番目の発言は又聞きだが、県内新聞社の新人教育体制だ。これは実際にわたしも日常顔を合わせている連中のことなので、手に取るように分かる。確かに新人教育のプロセスがなくなっているようだ。昔は警察を振り出しに、政治・経済・社会・地方といろんな部門を担当させて、適正の良いところに配置したのだが、いまはいきなり新人が経済部に配置され、企業側が発表するとおりの経済面記事を書いている。社内教育はゼロのようだ。
「基本的なことなんですがー」としょっちゅう携帯電話に電話がかかるけどどうなっているのと、無関係のわたしが県の部長から問い合わせを受けたこともある。どうも人脈維持のためのご機嫌伺いというのではなさそうで、本気で基本的なことを質問しているようなのだ。それだと社内にいくらでも専門家がいるはずなのに、と思う。仕方がないので「部長が好きなんじゃないですか」といってある。
製造業、学生を送り出す方の大学、文系の新聞社とそれぞれに本来の人材教育をだれかに押し付け、押し付けられているように見える。
「あと、2、30年もしたら日本は滅びるんでないかい」
Z君はかなり落ち着いて30年先の話をしているが、世界を不幸にしたグローバリズムをいまさら構造改革といって取り入れ、すでに日本は半分滅びているのではないかとわたしは思っているほどなのだが。
それをひっくり返す強力な抵抗勢力がいまはホントに必要であると思う。
Posted by 渡久地明 at 00:07│Comments(3)
│琉球の風(区別不能の原稿)
この記事へのコメント
最初の発言。
私も、まったくその通りだと思います。
企業側の方でもそういう認識を持たれている方がいらっしゃったことを教えて頂けてありがたく思います。
昨今の大手企業は、こぞってグループ内に‘人材派遣’部門を抱えています。ハローワークで見つける求人で、それを発見し、面接を受けてみました。
「実務経験が出来たら、お電話ください」と言われました。また、他社正社員との兼職可だそうです。人事担当者は、地元支社とは別の会社(当然ですが)の方で、わざわざ東京の方から出張して来られたそうです。地元支社のお偉いさんも同席しながら、訊いて来る質問は無意味なものばかり。しかも、人事担当者は勤務先の地名の呼び名を終始間違えておりました。
家の近所に在る某衛生陶器大手メーカなので、父に話したら、「もうどんな催し物でも行かない!」と言われました。
私は今月から、“経済産業省若年者雇用対策”の資格講座に滑り込むことが出来ました。資格が取得出来ても、「実務経験が…」とまた就職を断られるのが目に見えてます。(大学を卒業して12年経つのですが^^;)
私も、まったくその通りだと思います。
企業側の方でもそういう認識を持たれている方がいらっしゃったことを教えて頂けてありがたく思います。
昨今の大手企業は、こぞってグループ内に‘人材派遣’部門を抱えています。ハローワークで見つける求人で、それを発見し、面接を受けてみました。
「実務経験が出来たら、お電話ください」と言われました。また、他社正社員との兼職可だそうです。人事担当者は、地元支社とは別の会社(当然ですが)の方で、わざわざ東京の方から出張して来られたそうです。地元支社のお偉いさんも同席しながら、訊いて来る質問は無意味なものばかり。しかも、人事担当者は勤務先の地名の呼び名を終始間違えておりました。
家の近所に在る某衛生陶器大手メーカなので、父に話したら、「もうどんな催し物でも行かない!」と言われました。
私は今月から、“経済産業省若年者雇用対策”の資格講座に滑り込むことが出来ました。資格が取得出来ても、「実務経験が…」とまた就職を断られるのが目に見えてます。(大学を卒業して12年経つのですが^^;)
Posted by ふえきのり at 2006年10月01日 14:56
>他社正社員との兼職化
ですか。大学教授も副業化、というのと似てますね。
「実務経験はばりばりある」といって採用してもらっていいのでは。知り合いの社長に推薦状でも書いてもらえばよいですよ。相手だって、その一言が欲しいのでは。
中小企業での実務経験者がどんどんそういうところにとられると言うことでしょうね。中小企業たまらないなあ。
ちなみにわたしの経験では、ドイツの大学に入りたいが、実務経験が必要というので、わが社で2ヶ月トレーニングし、実務経験の証明書を発行して、無事合格・入学した者がいます。(非常に有能な青年でした)
ですか。大学教授も副業化、というのと似てますね。
「実務経験はばりばりある」といって採用してもらっていいのでは。知り合いの社長に推薦状でも書いてもらえばよいですよ。相手だって、その一言が欲しいのでは。
中小企業での実務経験者がどんどんそういうところにとられると言うことでしょうね。中小企業たまらないなあ。
ちなみにわたしの経験では、ドイツの大学に入りたいが、実務経験が必要というので、わが社で2ヶ月トレーニングし、実務経験の証明書を発行して、無事合格・入学した者がいます。(非常に有能な青年でした)
Posted by 渡久地明 at 2006年10月01日 18:25
いったい、「実務経験」てなんでしょうね^^?
「履歴書」でばれてしまいます。パート、アルバイトばかりで。
まず、“書類”でいくら話しても、聞く耳持たずの人事担当者が多いです。
テクノスクールで同期だった、「実務経験者」を見ていると、自分の経験が仇になっているようにしか見えませんでした。
「人事担当経験者」も首をひねっておりました。きちんと応対が出来て、身だしなみがしっかりしていれば、採用したものだそうです^^;
中小企業の方がずっと待遇がいいのではないのでしょうか?(多人数での職場経験も問われました)
渡久地さんのような、物分かりのよい社長さんは当方地元にはおりません。
羨ましい。
「履歴書」でばれてしまいます。パート、アルバイトばかりで。
まず、“書類”でいくら話しても、聞く耳持たずの人事担当者が多いです。
テクノスクールで同期だった、「実務経験者」を見ていると、自分の経験が仇になっているようにしか見えませんでした。
「人事担当経験者」も首をひねっておりました。きちんと応対が出来て、身だしなみがしっかりしていれば、採用したものだそうです^^;
中小企業の方がずっと待遇がいいのではないのでしょうか?(多人数での職場経験も問われました)
渡久地さんのような、物分かりのよい社長さんは当方地元にはおりません。
羨ましい。
Posted by ふえきのり at 2006年10月01日 19:51