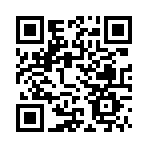2021年03月19日
沖縄経済同友会で講演、久々に懇親会

3月17日、2月7日にお知らせした、
沖縄観光の成り立ちと行く末
〜一工学者が観察した実際と成長原理〜
を1時間半、講演しました。会場に40人、zoomで十数人参加。大変好評、質疑応答も活発でした。沖縄ツーリスト東会長からこれまでみたことがない研究との評価をいただきました。
久々に懇親会にも参加しました。ご参集の皆様、ありがとうございました。
当日の次第です。
【当日のご案内】
≪委員会:第4回 観光委員会≫
日 時:令和3年3月17日(水)16:00~18:00
場 所:りゅうぎん健保会館 3階 大研修室(那覇市壷川1丁目1-9)
≪懇親会≫
日 時:令和3年3月17日(水) 18:00~20:00
場 所:メルキュールホテル沖縄那覇(那覇市壺川3-3-19)
============================================
当日の自分用のメモ(たくさん抜かしてしまいました)
沖縄経済同友会3/17講演メモ
(2021/3/9、今村さん最終講義の翌日、触発された部分あり。3/12、故・畔上先生「数の魔力」読み返して追加)
■琉球大理学部、法文学部、工学部で20年以上講義。工学部の故・玉城史朗教授が、絶賛。2015年からの「しまたてぃ」掲載レポートを博士論文としてまとめるよう2019年4月、勧告。20年6月までに6報を執筆、2本を研究会で発表。
■沖縄に特化した観察は初めて。沖縄に特化して観光の立ち上がりから途中経過、現在までの成り立ちを長期的に観察した例はない。現象に多角的に光を当て全体像を結ぼうとしている。1〜4報までの見通し1報に入れる。4報での意義を再度強調。
■Q&Aで①観察結果を数式に置き換える従来の科学②指数関数③ロジスティック方程式④周波数分析の初歩的な説明。
■受入体制(ホテル・供給)と観光客数(需要)の相互作用というこれまでなかった解釈。経済学ではケインズの「雇用・利子・お金の一般理論に十数ヵ所の言及あり」
■これまで供給と需要の両ポテンシャルの間の媒体(旅行社、最近はネットの情報)と媒達作用との考えはなかった。
■観光産業に新たに参入する投資家・事業者らがこれまでのチームに加わり、戦力が強化された。
■制度論の経済学者・青木昌彦氏が言う「実際、経済や社会のパフォーマンスは、政治的・経済的エリートによる法や組織のデザインと無数の人々による行動選択の相互作用で決まる、前者が後者の行動を完全に規定しうるのでもなければ、後者は受動的な砂粒のような存在に過ぎないのでもない」(「比較制度分析序説」269ページ)
■数理に基づく沖縄観光分析はなかった。マルサスの人口論、ロジスティック方程式、大腸菌(モデル生物)で実証。「大腸菌で成り立つことは象でも成り立つ」
■「Handbook OnTourism Forcasting Methodologies」(2008年)の重回帰の解説部分にプッシュファクター、プルファクターという電子回路の真空管やトランジスタの動作原理でお馴染みの記述。
■同書のCausal(因果モデル)の説明部分にコーザルが分かっている場合は分析は明快だが、わからないことが多いので実際には困難との記述。Causalの明快な例として為替レート、観光税を挙げている。
■目的地(陽極)と発地(陰極)の両ポテンシャルを埋める役割を長年にわたって旅行社がになってきたという役割(グリッド)との説明。
■観光客数のカウントが沖縄は最も正確。他の県は基準がない。観光庁の統一基準が2009年にできて、せいぜい12年。
■沖縄観光客数の伸び方に10年周期があることを発見。この10年周期は観光振興基本計画の10年目標の数値設定の影響があると思われる。
■一方、客室数に周期性はない。減ることがほとんどないからだ。道路や橋、トンネル、空港、港ができたことによって客室は増加が低迷したことはあっても、増え続けた。
■夏のビーチ・マリンリゾートに加え、1995年頃からの琉球文化のマーケティング活用(全日空)、2000年からの世界遺産。
■リゾートホテルが増え、沖縄本島西海岸でサミット。世界の首脳を迎えられるほど観光の質が向上。
■琉球大学教授らの「数量観光産業分析」、適切でない数理の使い方。(「数の魔力」に好例あり)
■JTBの「観光基礎」(2003)琉球大観光科学科の教科書、この本の構成は渡久地の「沖縄のリゾート業界入門」(1991)と瓜二つである。
■先駆者らの根拠なき信念で始まった沖縄観光? だが沖縄の美しさを全身で感じてそれに賭けた行動は大正解だった。アナログこそ人間の感覚。数式や文章などのデジタルからアナログに帰れ!(「数の魔力」畔上道雄) 未来を創るための「いま」=バック・トゥー・ザ・フューチャー!
=================================
当日配布の渡久地明略歴
有限会社 沖縄観光速報社、「観光とけいざい」編集発行人(代表取締役)
1957年 12月23日生 沖縄県出身
1979年 3月 群馬大学工学部電子工学科卒業
1981年 3月 同大大学院修了 電気工学専攻工学修士
1981年 4月 沖縄観光速報社入社・記者
・沖縄の観光産業の成り立ちについて、取材。この間、世界中を取材。
・琉球新報と共同で週刊レキオを企画創刊(1984年)
・OCVBから月刊の観光情報紙「マンスリーオキナワ」を企画創刊(1995年)
1991年 著書「沖縄のリゾート業界入門」(沖縄観光速報社)出版。
1995年 県内メディアで初めてホームページを開設、ニュースを公開。大変好評。
1997年 沖縄ケーブルネットワークの「おきなワ世紀末」「おきなわ新世紀」出演(2003年まで)。
番組中に「観光客1000万人ポリシー」(1998年10月)を発表。2016〜2017年の1000万人到達を予想。
1998年 メールマガジン「週刊おきなわファン」を発行。
2001年 琉球大学非常勤講師
2003年 観光情報学会(事務局:北海道大学) 設立発起人・理事、2005年から副会長(2年間)。
2004年 「沖縄観光成長の法則」発表。
2015年 「今後も伸びる沖縄観光成長の法則」(しまたてぃ73号)を発表。
2018年 沖縄観光客数が1000.4万人達成(2018年度ベース)、20年前の予想的中。
「観光とけいざい」「しまたてぃ」などでキャンプキンザーなどの再開発で15年後の観光客2000万人目標を主張。
那覇市観光功労者表彰。
2020年 電気学会発表会(2019年・琉球大学会場と2000年・沖縄総合事務局会場)で論文2本を発表。
Posted by 渡久地明 at 08:32│Comments(0)
│観光情報学の話題