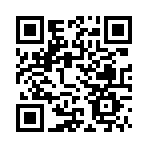› 渡久地明の時事解説 › 4月12日の記事
› 渡久地明の時事解説 › 4月12日の記事2021年04月12日
4月12日の記事
10年以上前の本だが、経済学に生物学でよく使われる自己組織化という考えを持ち込むキッカケとなったという。オレたちは40年前、学生時代に親しんだ考えで、当時の大型コンピュータでシミュレーションすることが流行っていた。
クルーグマンのこの見通しは、沖縄の観光産業のこれまでの成り立ちを振り返っても十分通用すると感じる。すなわち、観光客数を伸ばせば、道路や橋トンネル、港など社会インフラやホテル、観光施設などは自己組織化し、品質が高まり、さらに観光客を増やす。
渡久地がこれまで述べた観光客(需要)と受入体制(供給)の相互作用で観光産業が拡大したというのだいたい同じだ。
問題意識はなぜ、観光は伸びるのだろうかというもの。
「自己組織化」の112pには自己組織化システムが…経済にも適用できそうである。「しかしこのモデルでは、基本的な変化の原因は説明されていない。「成長と貿易論」で成長の原因が説明されていないのと一緒である」との記述がある。
結論部分(178〜179p)で「世界は、自己組織化システムで満ちている」。わたしは経済行動を説明するのにとりわけ有益な自己組織化に関する二つの原理を提示した」「第一の原理は不安定な状況から生じる秩序である」「第二の原理は、ランダムな状態から生じる秩序である」としている。
この次のページで自己組織化経済を考えるメリットは何であろうか。…「わたしの空間モデルが都市計画の役に立つかもしれないことは漠然と分かる」と続け、考察を終わりにしている(その後、補遺で数式を使って空間モデルを説明している)。
自己組織化システムで沖縄観光も成長してきたという考えを受け入れるなら、観光計画はインフラ整備など成長の促進策が最重要であることが理解されるはずだ。個別の施設建設やサービス内容などは各施設の独自の政策に任せておけば、自動的に最適化してゆくというわけだ。手抜きや品質の低下が広まらないような規制は必要かもしれない。
https://www.amazon.co.jp/dp/4480092560/ref=cm_sw_r_fa_dp_NSGKCAKERJJDZZ8BMA48?fbclid=IwAR3zCSB-c1eFa49x7u7fuElpOdF0CCRj9meyWqxcYVhY56t0qyWpzjcsVFY
クルーグマンのこの見通しは、沖縄の観光産業のこれまでの成り立ちを振り返っても十分通用すると感じる。すなわち、観光客数を伸ばせば、道路や橋トンネル、港など社会インフラやホテル、観光施設などは自己組織化し、品質が高まり、さらに観光客を増やす。
渡久地がこれまで述べた観光客(需要)と受入体制(供給)の相互作用で観光産業が拡大したというのだいたい同じだ。
問題意識はなぜ、観光は伸びるのだろうかというもの。
「自己組織化」の112pには自己組織化システムが…経済にも適用できそうである。「しかしこのモデルでは、基本的な変化の原因は説明されていない。「成長と貿易論」で成長の原因が説明されていないのと一緒である」との記述がある。
結論部分(178〜179p)で「世界は、自己組織化システムで満ちている」。わたしは経済行動を説明するのにとりわけ有益な自己組織化に関する二つの原理を提示した」「第一の原理は不安定な状況から生じる秩序である」「第二の原理は、ランダムな状態から生じる秩序である」としている。
この次のページで自己組織化経済を考えるメリットは何であろうか。…「わたしの空間モデルが都市計画の役に立つかもしれないことは漠然と分かる」と続け、考察を終わりにしている(その後、補遺で数式を使って空間モデルを説明している)。
自己組織化システムで沖縄観光も成長してきたという考えを受け入れるなら、観光計画はインフラ整備など成長の促進策が最重要であることが理解されるはずだ。個別の施設建設やサービス内容などは各施設の独自の政策に任せておけば、自動的に最適化してゆくというわけだ。手抜きや品質の低下が広まらないような規制は必要かもしれない。
https://www.amazon.co.jp/dp/4480092560/ref=cm_sw_r_fa_dp_NSGKCAKERJJDZZ8BMA48?fbclid=IwAR3zCSB-c1eFa49x7u7fuElpOdF0CCRj9meyWqxcYVhY56t0qyWpzjcsVFY
Posted by 渡久地明 at 09:47│Comments(0)