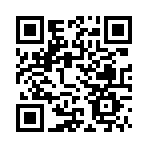2007年06月30日
日章旗は進貢船の船印
琉球諸島の2009年問題というのがある。それについて、「観光とけいざい」第724号(07年6月15日付)で触れた。その中で、「日章旗はもともと琉球の旗として中国への進貢船で使われていた」というウィキペディアの解説を引用したところ、琉球歴史に詳しいある社長から電話がかかってきた。
「渡久地君、日章旗が琉球の旗だったという話は、わたしも15年ほど前に進貢船の調査をしていて、沖縄の大学教授から聞いたことがある。ただし教授は、
『そこまで調べたのなら、お話しするが、日章旗は進貢船が使っていた旗であったという話を他の研究者から聞いたことがある。わたしはその文献なり証拠を見ていないので、断定はできないが、…』
とのことだった。
そのウィキペディアというのは何かね。沖縄の歴史の中で言ってはいけないことのように感じていたが、そんなのが堂々と出ているのかい」
という問い合わせである。(ウィキペディアプロジェクトについて説明したのは言うまでもない。)
ところが、わたしも日章旗が進貢船の船印だったとは知らなかったのだ。ウィキペディアに出ているくらいなら常識なんだろうという認識しかなかった。たしか、琉球国の国旗があった、それが再発見されたという新聞記事はむかーし、見たことがあるが、それは日の丸とは異なるものだった。ウィキペディアのこの記述は常識なのだろうか。詳しい人がいたら教えて下さい。
なお、沖縄の歴史で突拍子もないことはいくらでもあ。源為朝が沖縄まで来ていて、その子が後の舜天王になったとか、民間伝承ではいろいろなものがある。もっとすごいのは卑弥呼は沖縄の女王だったというものもある(わたしはこれは本当ではないかと思っている。ただし日本の卑弥呼の遙か前の時代)。これらは学会や学者の世界では全く語られない。話題にした瞬間にバカにされる雰囲気がある。
日章旗に関する話題も社長はその類のものと思いこんでいたらしい。しかし、そのような伝承の中に事実もときどき紛れ込んでいるというのは古今東西の歴史が証明している。沖縄の職業学者が書く歴史書が面白くないのは、証拠があるものだけ書く、という姿勢だからではないか。(続きを読む、に冒頭に紹介したコラムを再掲した)
「渡久地君、日章旗が琉球の旗だったという話は、わたしも15年ほど前に進貢船の調査をしていて、沖縄の大学教授から聞いたことがある。ただし教授は、
『そこまで調べたのなら、お話しするが、日章旗は進貢船が使っていた旗であったという話を他の研究者から聞いたことがある。わたしはその文献なり証拠を見ていないので、断定はできないが、…』
とのことだった。
そのウィキペディアというのは何かね。沖縄の歴史の中で言ってはいけないことのように感じていたが、そんなのが堂々と出ているのかい」
という問い合わせである。(ウィキペディアプロジェクトについて説明したのは言うまでもない。)
ところが、わたしも日章旗が進貢船の船印だったとは知らなかったのだ。ウィキペディアに出ているくらいなら常識なんだろうという認識しかなかった。たしか、琉球国の国旗があった、それが再発見されたという新聞記事はむかーし、見たことがあるが、それは日の丸とは異なるものだった。ウィキペディアのこの記述は常識なのだろうか。詳しい人がいたら教えて下さい。
なお、沖縄の歴史で突拍子もないことはいくらでもあ。源為朝が沖縄まで来ていて、その子が後の舜天王になったとか、民間伝承ではいろいろなものがある。もっとすごいのは卑弥呼は沖縄の女王だったというものもある(わたしはこれは本当ではないかと思っている。ただし日本の卑弥呼の遙か前の時代)。これらは学会や学者の世界では全く語られない。話題にした瞬間にバカにされる雰囲気がある。
日章旗に関する話題も社長はその類のものと思いこんでいたらしい。しかし、そのような伝承の中に事実もときどき紛れ込んでいるというのは古今東西の歴史が証明している。沖縄の職業学者が書く歴史書が面白くないのは、証拠があるものだけ書く、という姿勢だからではないか。(続きを読む、に冒頭に紹介したコラムを再掲した)
琉球諸島の2009年問題(「観光とけいざい」第724号、6月15日付コラム「視点」)
沖縄には二〇〇九年問題というのがある。二〇〇九年問題とは、一六〇九年から四百年目ということで、一六〇九年とは薩摩が琉球に侵攻した年である。
ネット上の辞書ウィキペディアには「薩摩」の項に琉球侵攻について次の記述がある。
「一六〇九年(慶長十四年)、琉球に出兵して琉球王朝を服属させ、琉球の石高十二万石を加えられた。奄美諸島は沖縄と分離され、薩摩藩が直接支配した。薩摩藩の琉球支配は、年貢よりもむしろ琉球王朝を窓口にした中国との貿易が利益をもたらした。また、薩摩には奄美産の砂糖による利益がもたらされた。その他加増を受けて七十七万石の大藩となる」。
この薩摩の琉球侵攻というのは現代の沖縄でもよく話題になる。同じことが奄美諸島の人たちの間でも話題になる。さまざまな問題を含んでいると思うが、明治維新で薩摩が有利なポジションをとったのは琉球のサトウキビや外国貿易で得られた利益がその原動力となったというものだ。ペリー提督の黒船が来たのも琉球を足がかりにしており、その時の詳細な情報が琉球から薩摩経由で江戸にも伝えられる。
外に開かれた琉球の情報力も明治維新を導いた薩摩に有利に作用した。琉球のおかげで明治維新は実現したということになるわけだ。
それがどうした、という声が聞こえてきそうだが、それをどうにかしようではないかということが、二〇〇九年問題には含まれている。
与論島から種子島の手前までの奄美諸島の人たちの中には鹿児島県でいるより、琉球になった方が発展するのではないかとの見方がある。
一方、沖縄県よりも琉球の方が東南アジアにとってなじみが深いという事実もある。
日章旗はもともと琉球の国旗だったのを日本が借用して、いつのまにか日本の国旗になった。
ウィキペディアの「日章旗」の項には「船印としては、薩摩藩に服属していた琉球王国が中国への進貢船に日章旗を用いており、江戸時代後期からは薩摩藩の船印としても用いられるようになった。開国後は幕府が日本国共通の船舶旗(船印)を制定する必要が生じたときに、薩摩藩からの進言(進言したのは薩摩藩主、島津斉彬だといわれる)で日章旗を用いることになった。一般的に日本を象徴する旗として公式に用いられるようになったのはこれが最初であるとされる(略)」。
もっと遡ると、三万八千年前という古い人の骨は日本では沖縄だけから出ている。沖縄人が日本人の源流であったという学説は有力である。
沖縄というのはいまは日本の一県ということだが、たったの四百年くらい前には東南アジアの有力な国家として繁栄していたことが、世界に知られている。四百年前の出来事にキリがいいのでケリを付けようというのが二〇〇九年問題ではないかと思う。(明)
沖縄には二〇〇九年問題というのがある。二〇〇九年問題とは、一六〇九年から四百年目ということで、一六〇九年とは薩摩が琉球に侵攻した年である。
ネット上の辞書ウィキペディアには「薩摩」の項に琉球侵攻について次の記述がある。
「一六〇九年(慶長十四年)、琉球に出兵して琉球王朝を服属させ、琉球の石高十二万石を加えられた。奄美諸島は沖縄と分離され、薩摩藩が直接支配した。薩摩藩の琉球支配は、年貢よりもむしろ琉球王朝を窓口にした中国との貿易が利益をもたらした。また、薩摩には奄美産の砂糖による利益がもたらされた。その他加増を受けて七十七万石の大藩となる」。
この薩摩の琉球侵攻というのは現代の沖縄でもよく話題になる。同じことが奄美諸島の人たちの間でも話題になる。さまざまな問題を含んでいると思うが、明治維新で薩摩が有利なポジションをとったのは琉球のサトウキビや外国貿易で得られた利益がその原動力となったというものだ。ペリー提督の黒船が来たのも琉球を足がかりにしており、その時の詳細な情報が琉球から薩摩経由で江戸にも伝えられる。
外に開かれた琉球の情報力も明治維新を導いた薩摩に有利に作用した。琉球のおかげで明治維新は実現したということになるわけだ。
それがどうした、という声が聞こえてきそうだが、それをどうにかしようではないかということが、二〇〇九年問題には含まれている。
与論島から種子島の手前までの奄美諸島の人たちの中には鹿児島県でいるより、琉球になった方が発展するのではないかとの見方がある。
一方、沖縄県よりも琉球の方が東南アジアにとってなじみが深いという事実もある。
日章旗はもともと琉球の国旗だったのを日本が借用して、いつのまにか日本の国旗になった。
ウィキペディアの「日章旗」の項には「船印としては、薩摩藩に服属していた琉球王国が中国への進貢船に日章旗を用いており、江戸時代後期からは薩摩藩の船印としても用いられるようになった。開国後は幕府が日本国共通の船舶旗(船印)を制定する必要が生じたときに、薩摩藩からの進言(進言したのは薩摩藩主、島津斉彬だといわれる)で日章旗を用いることになった。一般的に日本を象徴する旗として公式に用いられるようになったのはこれが最初であるとされる(略)」。
もっと遡ると、三万八千年前という古い人の骨は日本では沖縄だけから出ている。沖縄人が日本人の源流であったという学説は有力である。
沖縄というのはいまは日本の一県ということだが、たったの四百年くらい前には東南アジアの有力な国家として繁栄していたことが、世界に知られている。四百年前の出来事にキリがいいのでケリを付けようというのが二〇〇九年問題ではないかと思う。(明)
Posted by 渡久地明 at 15:45│Comments(4)
│琉球の風(区別不能の原稿)
この記事へのコメント
おととい、友達が宮古島旅行から帰って来て
友人数人と飲んでいたら、日章旗の話になり
元々、琉球王朝時代に使われていた旗らしく
それを付ける事により海賊などから襲われにくくなる
また、見方を識別するなどに使われていたらしいと言う話で
たまたま、漁師の祭りで船に日章旗が付けられていて
それがなぜか来てみた友達もいて漁師の人の話では
もともと、琉球時代から付けていたで薩摩の時代に
日本に持って行かれた物だと言うストーリーを聴いたそうです。
紅芋は、さつま芋にされ持って行かれたり
宮古上布も薩摩上布として薩摩で売っていた事も有り
これもまた奪い取った歴史があるので
日章旗は琉球時代に琉球の物である事もたしかなのかもしれません
話はかわりますが、
久高島の人は航海士の帆船技術があり
台湾に近い与那国島に親戚が多いことに
まだまだ謎の多い歴史が眠っていそうです。
琉球王朝前、三山時代? それよりずーと前といっても
600年前、その歴史は残っていないのが不思議に思います。
友人数人と飲んでいたら、日章旗の話になり
元々、琉球王朝時代に使われていた旗らしく
それを付ける事により海賊などから襲われにくくなる
また、見方を識別するなどに使われていたらしいと言う話で
たまたま、漁師の祭りで船に日章旗が付けられていて
それがなぜか来てみた友達もいて漁師の人の話では
もともと、琉球時代から付けていたで薩摩の時代に
日本に持って行かれた物だと言うストーリーを聴いたそうです。
紅芋は、さつま芋にされ持って行かれたり
宮古上布も薩摩上布として薩摩で売っていた事も有り
これもまた奪い取った歴史があるので
日章旗は琉球時代に琉球の物である事もたしかなのかもしれません
話はかわりますが、
久高島の人は航海士の帆船技術があり
台湾に近い与那国島に親戚が多いことに
まだまだ謎の多い歴史が眠っていそうです。
琉球王朝前、三山時代? それよりずーと前といっても
600年前、その歴史は残っていないのが不思議に思います。
Posted by プクプク at 2007年10月29日 20:50
県立博物館で11月1日から
人類の旅 港川人の来た道
が開かれますが、内容はほぼこれ↓
http://www.kahaku.go.jp/special/past/japanese/ipix/index.html
と同じじゃないかと想像しています(主催者も同じ)。
最初に日本にたどり着いたのは港川人の仲間だった沖縄人で、それが日本全体に広がっていったと。上記サイトには港川人が縄文人になったというようなことが書いてあります。
日本考古学のあのでっち上げ石器事件で、沖縄の山下洞人が日本最古の人骨化石で、同時に石器が出た最重要遺跡と再認識されます。沖縄から人が行くまで、日本には誰も住んでいなかったと歴史が書き換えられたわけです。
だから、ひとをはじめいろんなものが3万年以上も前から黒潮にのって沖縄経由で日本に入っていたわけで、それが芋や日章旗も含め現在までズーッと続いていると考えて正解なのでは。
ちなみに焼酎も沖縄泡盛がルーツです。また、泡盛ができたのは1400年代で、ウイスキーと同じ時期です。
人類の旅 港川人の来た道
が開かれますが、内容はほぼこれ↓
http://www.kahaku.go.jp/special/past/japanese/ipix/index.html
と同じじゃないかと想像しています(主催者も同じ)。
最初に日本にたどり着いたのは港川人の仲間だった沖縄人で、それが日本全体に広がっていったと。上記サイトには港川人が縄文人になったというようなことが書いてあります。
日本考古学のあのでっち上げ石器事件で、沖縄の山下洞人が日本最古の人骨化石で、同時に石器が出た最重要遺跡と再認識されます。沖縄から人が行くまで、日本には誰も住んでいなかったと歴史が書き換えられたわけです。
だから、ひとをはじめいろんなものが3万年以上も前から黒潮にのって沖縄経由で日本に入っていたわけで、それが芋や日章旗も含め現在までズーッと続いていると考えて正解なのでは。
ちなみに焼酎も沖縄泡盛がルーツです。また、泡盛ができたのは1400年代で、ウイスキーと同じ時期です。
Posted by 渡久地明 at 2007年10月30日 22:53
at 2007年10月30日 22:53
 at 2007年10月30日 22:53
at 2007年10月30日 22:53泡盛は
タイのメコン酒が原型といわれており
また面白いのが(サバニ)の形と同じ船が多いと言う事です。
サバニで昔はタイ王国まで旧琉球人は来ていたのかもしれません
サバニに日章旗と同じデザインがされていたのは確かで
見方の識別などしていたそうです。
海賊に襲われそうになると空手で応戦した誇り高い海人の話など
ゴホウラガイなど神道のルーツが沖縄にあるのも確かな事で
600年前の歴史は簡単に見つけにくいのです。
沖縄 →沖の縄文 とも隠された隠語でもあるかも知れません
バリ島では
チャンプルーなど風習と語源が沖縄に近く
遠い昔のポリネシア文化というルーツが渡航技術のある
琉球を作ったと言う事かもしれません
台湾などの山岳民族の衣装の模様など色など
タイの山岳民族も同じようなもので南米など
民族はどこにいっても同じ格好が多い事に
また歴史が2万年など古い歴史の中に争わない支配しない
縄文的暮らしに豊かな暮らしがある訳です。
映画ブッシュマンなどでおなじみのコイ族サン族
歴史は2万年もあり黄色人種 、
ピラミッドの文明はまだ五千年もたっていません。
タイのメコン酒が原型といわれており
また面白いのが(サバニ)の形と同じ船が多いと言う事です。
サバニで昔はタイ王国まで旧琉球人は来ていたのかもしれません
サバニに日章旗と同じデザインがされていたのは確かで
見方の識別などしていたそうです。
海賊に襲われそうになると空手で応戦した誇り高い海人の話など
ゴホウラガイなど神道のルーツが沖縄にあるのも確かな事で
600年前の歴史は簡単に見つけにくいのです。
沖縄 →沖の縄文 とも隠された隠語でもあるかも知れません
バリ島では
チャンプルーなど風習と語源が沖縄に近く
遠い昔のポリネシア文化というルーツが渡航技術のある
琉球を作ったと言う事かもしれません
台湾などの山岳民族の衣装の模様など色など
タイの山岳民族も同じようなもので南米など
民族はどこにいっても同じ格好が多い事に
また歴史が2万年など古い歴史の中に争わない支配しない
縄文的暮らしに豊かな暮らしがある訳です。
映画ブッシュマンなどでおなじみのコイ族サン族
歴史は2万年もあり黄色人種 、
ピラミッドの文明はまだ五千年もたっていません。
Posted by 泡盛 at 2007年12月03日 17:41
>泡盛さん
サバニに日の丸があったんですか。現物を見てみたかったですね。もう昔のものはないでしょうね。
県博がオープンしたころ、NHK教育テレビで日本人のルーツをミトコンドリアDNAから探る特集をしていましたが、沖縄は明らかに東南アジア系(日本人の多く(東南アジアやミクロネシア、南北アメリカ大陸も)も沖縄と同じ祖先ですが、朝鮮半島系のDNAの比率が高くなるということでした)。1000年前の歴史より、もっと大昔のことの方が面白いと思っています。
サバニに日の丸があったんですか。現物を見てみたかったですね。もう昔のものはないでしょうね。
県博がオープンしたころ、NHK教育テレビで日本人のルーツをミトコンドリアDNAから探る特集をしていましたが、沖縄は明らかに東南アジア系(日本人の多く(東南アジアやミクロネシア、南北アメリカ大陸も)も沖縄と同じ祖先ですが、朝鮮半島系のDNAの比率が高くなるということでした)。1000年前の歴史より、もっと大昔のことの方が面白いと思っています。
Posted by 渡久地明 at 2007年12月04日 21:35
at 2007年12月04日 21:35
 at 2007年12月04日 21:35
at 2007年12月04日 21:35