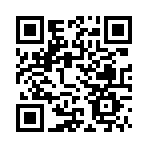2008年04月03日
後期高齢者医療制度の哀れ
佐々木洋氏のメルマガ「10秒で読む日経」(08年3月28日付)
http://archive.mag2.com/0000102800/20080328111000001.html
に後期高齢者医療制度について、出色のコメントがあった。
====================
佐々木の視点・考え方
★4月から医療制度が変る。主な変更は高齢層だ。内容は、
・65〜74歳の高齢者の国民健康保険料を年金から天引き
・70〜74歳の患者の窓口負担を1割から2割に引き上げ
・75歳以上の人を「後期高齢者」と呼び、ほかの世代と切り離した医療保険制度に加入することになる。
新制度では、75歳以上の人は今まで入っていた保険を脱退させられるため、夫75歳、妻70歳の場合は、これまで同じ保険制度だったものが別のシステム、医療体制になる。
・75歳以上のすべての人から保険料を徴収。年金額が月1.5万円以上の人は保険料を年金から天引き
これまで扶養家族として支払い義務がなかった約2百万人の高齢者が、新規で保険料を払わなければならなくなる。
高齢者の大多数が、収入は年金からに頼り切っている。この年金から天引きするシステムのため、手取り可処分所得が減る。
・保険料滞納者からは保険証を取り上げ、資格証明書を発行病院の窓口でかかった医療費を全額(十割)支払うことになる。
1年以上保険料を滞納すれば、保険証を取り上げられ、代わりに資格証明書が発行される。保険料滞納者は、唯一の収入の年金が少なくて個別納付しているのだから、実質的に病院に行くことが出来なくなる。
・後期高齢医療制度は診療報酬を現役世代とは別建てにして、保険で受けられる医療に制限をつける等を予定している。
社会保障審議会特別部会の「診療報酬体系の骨子」によると、新制度で75歳以上が受けられる医療は、「治療の長期化が見られる」「いずれ死を迎える」と特徴づけ、それに見合った格安の医療にとどめることを求めている。
後期高齢医療制度の保険料は、健保・国保など現役世代の医療保険からの支援が40%、国・自治体負担が50%、被保険高齢者自身の負担が10%となっている。
この記事の保険料とは、10%を占める高齢者の負担額が、各自治体でどう変るかを示したもの。
保険料は2年ごとに改定される。しかし、この制度の目的が高齢者医療費の削減であるため、改定のたびに後期高齢者の保険料を徐々に増やして行く予定。
★このメルマガの読者で後期高齢医療制度に該当する人はかなり少ない。だから、「しょせんひとごとでしょ。」と思われたろう。
それは間違い。この制度の本質はこうだ。
両親や祖父母がシビアな状態になったとき(残念ながらいつかは必ずやって来る)に、医師から「保険では出ませんので、退院してください」とか、「ICUから出てください」と言われる事になる。
その時、「幾ら高額でも、医療費を10割全額現金で支払いますから両親や祖父母に医療を受けさせてください」と、あなたが言える(それだけの経済準備をしている)か、言えずに「親に満足な医療を受けさせてやれなかった」と後で後悔し続けるかのいずれかの立場に、あなたがなるということだ。
「老後の準備」には、こうした現状への対応も含めなければいけない。
====================
「シッコ」や「貧困大陸アメリカ」で見た市場原理主義に基づく医療制度の典型例が後期高齢者医療制度というわけだ。満足な医療が受けられず哀れに死んでいくお年寄り。それを後悔し続ける若い世代。これが何代も続くとどんな国になるのだろうかと思う。こんな制度は早く取り消し、今まで通りにすべきだ。これが改革とは…。解決策は今まで何度も述べたように積極(以下略)
http://archive.mag2.com/0000102800/20080328111000001.html
に後期高齢者医療制度について、出色のコメントがあった。
====================
佐々木の視点・考え方
★4月から医療制度が変る。主な変更は高齢層だ。内容は、
・65〜74歳の高齢者の国民健康保険料を年金から天引き
・70〜74歳の患者の窓口負担を1割から2割に引き上げ
・75歳以上の人を「後期高齢者」と呼び、ほかの世代と切り離した医療保険制度に加入することになる。
新制度では、75歳以上の人は今まで入っていた保険を脱退させられるため、夫75歳、妻70歳の場合は、これまで同じ保険制度だったものが別のシステム、医療体制になる。
・75歳以上のすべての人から保険料を徴収。年金額が月1.5万円以上の人は保険料を年金から天引き
これまで扶養家族として支払い義務がなかった約2百万人の高齢者が、新規で保険料を払わなければならなくなる。
高齢者の大多数が、収入は年金からに頼り切っている。この年金から天引きするシステムのため、手取り可処分所得が減る。
・保険料滞納者からは保険証を取り上げ、資格証明書を発行病院の窓口でかかった医療費を全額(十割)支払うことになる。
1年以上保険料を滞納すれば、保険証を取り上げられ、代わりに資格証明書が発行される。保険料滞納者は、唯一の収入の年金が少なくて個別納付しているのだから、実質的に病院に行くことが出来なくなる。
・後期高齢医療制度は診療報酬を現役世代とは別建てにして、保険で受けられる医療に制限をつける等を予定している。
社会保障審議会特別部会の「診療報酬体系の骨子」によると、新制度で75歳以上が受けられる医療は、「治療の長期化が見られる」「いずれ死を迎える」と特徴づけ、それに見合った格安の医療にとどめることを求めている。
後期高齢医療制度の保険料は、健保・国保など現役世代の医療保険からの支援が40%、国・自治体負担が50%、被保険高齢者自身の負担が10%となっている。
この記事の保険料とは、10%を占める高齢者の負担額が、各自治体でどう変るかを示したもの。
保険料は2年ごとに改定される。しかし、この制度の目的が高齢者医療費の削減であるため、改定のたびに後期高齢者の保険料を徐々に増やして行く予定。
★このメルマガの読者で後期高齢医療制度に該当する人はかなり少ない。だから、「しょせんひとごとでしょ。」と思われたろう。
それは間違い。この制度の本質はこうだ。
両親や祖父母がシビアな状態になったとき(残念ながらいつかは必ずやって来る)に、医師から「保険では出ませんので、退院してください」とか、「ICUから出てください」と言われる事になる。
その時、「幾ら高額でも、医療費を10割全額現金で支払いますから両親や祖父母に医療を受けさせてください」と、あなたが言える(それだけの経済準備をしている)か、言えずに「親に満足な医療を受けさせてやれなかった」と後で後悔し続けるかのいずれかの立場に、あなたがなるということだ。
「老後の準備」には、こうした現状への対応も含めなければいけない。
====================
「シッコ」や「貧困大陸アメリカ」で見た市場原理主義に基づく医療制度の典型例が後期高齢者医療制度というわけだ。満足な医療が受けられず哀れに死んでいくお年寄り。それを後悔し続ける若い世代。これが何代も続くとどんな国になるのだろうかと思う。こんな制度は早く取り消し、今まで通りにすべきだ。これが改革とは…。解決策は今まで何度も述べたように積極(以下略)
Posted by 渡久地明 at 20:23│Comments(0)
│デフレ脱却