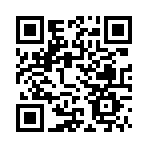2009年03月18日
夕刊廃止の原因は何か
三月から県内日刊紙「新報」「タイムス」の夕刊が廃止された。部数が伸びないうえ、広告収入が激減している。収入が増やせないのでコストカットに走るしかなくなったようだ。沖縄に限らず、日本中でマスコミの経営が厳しい。
なぜ、そうなったのか。
答は簡単。自分で世の中の景気を悪くするような記事を垂れ流し続けた結果、多くの国民の給料が減り、デフレが進行。先行き一層の不況に備えて財布の紐を締めたからだ。
新聞は過去30年にわたって市場原理が常に正しいものと誤解して、大きな政府より小さな政府、官僚や公共事業悪玉論を展開し、政府の借金を減らすことが大切だと説いた。その結果、90年のバブル崩壊を契機に政治の世界でもそれまで影を潜めていた市場原理主義者の発言力が強くなり、景気はどんどん悪くなった。橋本首相時代の行財政改革、小泉首相の構造改革は景気回復の腰を折った。
間違った経済理論の普及にマスコミは貢献した。郵便局を民営化したら景気は良くなると言う、どう考えても景気とは無関係な理屈を唱える政治家・小泉純一郎やおかしな経済学者・竹中平蔵をもてはやした。狂った政治家でもマスコミが持ち上げると票がとれるのだった。ドイツにも昔そういう政治家がいたなあ。
郵便局民営化の結果はご覧の通り。不正のオンパレードである。郵便局民営化に反対した人たちは、国民の資産をハゲタカ外資に献上するようなものだと当初から批判していた。アメリカの保険会社や投資銀行が簡保や郵貯のカネを狙っているというものだったが、最近の事件の数々はそれが杞憂ではなく、現実であったことを明らかにした。市場原理主義ではなく、構造改革を唱えたお友達社会主義だった。
グローバリズムという言葉もまるで当たり前のように報道されてきた。グローバリズムに乗り遅れると競争力のない日本企業は倒産してしまうというものだった。しかし、日本のトップ産業である自動車や電気はすでに世界中で仕事をしていた。90年代後半に言われたグローバリズムは主に金融機関向けのスローガンだった。
ところが、金融機関をわざわざグローバル化する意義はあまりなかった。ほとんどの金融機関が国内で仕事をしており、特定の金融機関が国際的な仕事をする場合は別として、地域の銀行にグローバルスタンダードなどどうでもいいことだった。地域の中小企業にまともにカネを供給し、カネを貸した先がグローバルに育つよう工夫すれば良かった。金融機関の手足を縛るおかしなグローバルスタンダードの導入で金融機関は誰のための、何のための存在か分からなくなってしまった。
一つの企業で一生勤めるのではなく、働く自由が必要だとして、派遣社員制度があらゆる業種に導入されたが、不況時には真っ先に派遣をはじめパート、アルバイトの仕事がなくなった。もし世の中が好況なら派遣制度の導入以前に、企業はいつでも人手が必要で、社員は待遇の悪いところからは逃げ出し、いくらでもよいところに移れただろう。
もともと派遣制度は特定の業種を除いてそれほど社会にとっと必要とされるものではなかった。唯一、不況を予測し、不況によって利益をあげる計画をたてた企業が利益を得た。
わたし自身も90年代後半から日本は恐慌のような状態に入っていると認識した。日本経済復活の会や丹羽春喜教授の論説が正しく日本の現状を説明していると思った。そのまま行くと大変なことになるのが見えたので、そこに行き着かなくさせるためにこのさまざまな媒体で発言したが、まったく相手にされなかった。
しかし、最近になってやっと世界中で市場原理主義が間違いだったことが理解されるようになってきた。その結果オバマ大統領が出てきたり、クルーグマン教授がノーベル賞を取ったりしたことで、政府の役割が改めて注目されるようになってきた。
アメリカでは国民にカネをバラ撒いた方がよいのか、公共工事をやった方が効果があるのかという論争が有力経済学者の間で起こっているのに、日本のマスコミは最後まで間違った市場原理主義の旗を降ろしていない。いまだに小泉構造改革を止めてはならないというバカ学者を優遇しているのがその証拠だ。その結果、大胆な財政出動で景気を本格的に回復させることができず、国民は政府もマスコミも信用しなくなった。
話はそれるが、民主党の小沢一郎党首の献金疑惑にたいする国民の反応が面白い。支持率が思ったより下がらないうえ、多くのブロガーが国策捜査だとさまざまな証拠を挙げて主張している。わたしも、おかしなタイミングでの変な捜査が行われたものだという感じている。同時に、何でこれほどマスコミは小沢さんを目の敵にしているのか不思議でたまらない。報道は明らかに偏っていると思う。マスコミが信用されなくなったのだ。
むかしは沖縄の新聞社は命がけで新聞発行を維持し、その間業績はあがったが、最近はとうとう背に腹は代えられないと夕刊を廃止した。そうせざるを得なくなった原因をもっと深く追求すべきだ。
すると東京の新聞と地域の新聞は同じような記事の書き方をしてはいけないということに気がつくだろう。地方の新聞は東京に対して「おまえは間違っている」と声を挙げ、実際につながりも深いようだから乗り込んでいって説教するくらいでないといけない。
ついでにいうと「日経」が沖縄で印刷を始めたが、地元の新聞を取るのを止めて「日経」一紙に変える人が結構いるという。「日経」は日本を不況に陥れた戦犯の一人であり、「日経」だけを読むというのは沖縄にとって決してよい傾向ではない。この点でも沖縄の新聞社は日本の景気を悪くするのに手をかしているわけだ。
県内新聞の夕刊廃止というのは大きな失態で、市場原理主義の失敗の典型例だと思うが、誰もそれを指摘しない。どうでもいいと思われる存在に成り下がっていたのかも知れない。
25年くらい前までの新聞社の社長達の方がいまよりはるかに責任感が強かったと思う。おかげで当の社長も社員も苦労していたが、いまは「儲からないならやーめた」と気楽なものだ。自分の存在意義を捨てたとしか見えないのだ。
なぜ、そうなったのか。
答は簡単。自分で世の中の景気を悪くするような記事を垂れ流し続けた結果、多くの国民の給料が減り、デフレが進行。先行き一層の不況に備えて財布の紐を締めたからだ。
新聞は過去30年にわたって市場原理が常に正しいものと誤解して、大きな政府より小さな政府、官僚や公共事業悪玉論を展開し、政府の借金を減らすことが大切だと説いた。その結果、90年のバブル崩壊を契機に政治の世界でもそれまで影を潜めていた市場原理主義者の発言力が強くなり、景気はどんどん悪くなった。橋本首相時代の行財政改革、小泉首相の構造改革は景気回復の腰を折った。
間違った経済理論の普及にマスコミは貢献した。郵便局を民営化したら景気は良くなると言う、どう考えても景気とは無関係な理屈を唱える政治家・小泉純一郎やおかしな経済学者・竹中平蔵をもてはやした。狂った政治家でもマスコミが持ち上げると票がとれるのだった。ドイツにも昔そういう政治家がいたなあ。
郵便局民営化の結果はご覧の通り。不正のオンパレードである。郵便局民営化に反対した人たちは、国民の資産をハゲタカ外資に献上するようなものだと当初から批判していた。アメリカの保険会社や投資銀行が簡保や郵貯のカネを狙っているというものだったが、最近の事件の数々はそれが杞憂ではなく、現実であったことを明らかにした。市場原理主義ではなく、構造改革を唱えたお友達社会主義だった。
グローバリズムという言葉もまるで当たり前のように報道されてきた。グローバリズムに乗り遅れると競争力のない日本企業は倒産してしまうというものだった。しかし、日本のトップ産業である自動車や電気はすでに世界中で仕事をしていた。90年代後半に言われたグローバリズムは主に金融機関向けのスローガンだった。
ところが、金融機関をわざわざグローバル化する意義はあまりなかった。ほとんどの金融機関が国内で仕事をしており、特定の金融機関が国際的な仕事をする場合は別として、地域の銀行にグローバルスタンダードなどどうでもいいことだった。地域の中小企業にまともにカネを供給し、カネを貸した先がグローバルに育つよう工夫すれば良かった。金融機関の手足を縛るおかしなグローバルスタンダードの導入で金融機関は誰のための、何のための存在か分からなくなってしまった。
一つの企業で一生勤めるのではなく、働く自由が必要だとして、派遣社員制度があらゆる業種に導入されたが、不況時には真っ先に派遣をはじめパート、アルバイトの仕事がなくなった。もし世の中が好況なら派遣制度の導入以前に、企業はいつでも人手が必要で、社員は待遇の悪いところからは逃げ出し、いくらでもよいところに移れただろう。
もともと派遣制度は特定の業種を除いてそれほど社会にとっと必要とされるものではなかった。唯一、不況を予測し、不況によって利益をあげる計画をたてた企業が利益を得た。
わたし自身も90年代後半から日本は恐慌のような状態に入っていると認識した。日本経済復活の会や丹羽春喜教授の論説が正しく日本の現状を説明していると思った。そのまま行くと大変なことになるのが見えたので、そこに行き着かなくさせるためにこのさまざまな媒体で発言したが、まったく相手にされなかった。
しかし、最近になってやっと世界中で市場原理主義が間違いだったことが理解されるようになってきた。その結果オバマ大統領が出てきたり、クルーグマン教授がノーベル賞を取ったりしたことで、政府の役割が改めて注目されるようになってきた。
アメリカでは国民にカネをバラ撒いた方がよいのか、公共工事をやった方が効果があるのかという論争が有力経済学者の間で起こっているのに、日本のマスコミは最後まで間違った市場原理主義の旗を降ろしていない。いまだに小泉構造改革を止めてはならないというバカ学者を優遇しているのがその証拠だ。その結果、大胆な財政出動で景気を本格的に回復させることができず、国民は政府もマスコミも信用しなくなった。
話はそれるが、民主党の小沢一郎党首の献金疑惑にたいする国民の反応が面白い。支持率が思ったより下がらないうえ、多くのブロガーが国策捜査だとさまざまな証拠を挙げて主張している。わたしも、おかしなタイミングでの変な捜査が行われたものだという感じている。同時に、何でこれほどマスコミは小沢さんを目の敵にしているのか不思議でたまらない。報道は明らかに偏っていると思う。マスコミが信用されなくなったのだ。
むかしは沖縄の新聞社は命がけで新聞発行を維持し、その間業績はあがったが、最近はとうとう背に腹は代えられないと夕刊を廃止した。そうせざるを得なくなった原因をもっと深く追求すべきだ。
すると東京の新聞と地域の新聞は同じような記事の書き方をしてはいけないということに気がつくだろう。地方の新聞は東京に対して「おまえは間違っている」と声を挙げ、実際につながりも深いようだから乗り込んでいって説教するくらいでないといけない。
ついでにいうと「日経」が沖縄で印刷を始めたが、地元の新聞を取るのを止めて「日経」一紙に変える人が結構いるという。「日経」は日本を不況に陥れた戦犯の一人であり、「日経」だけを読むというのは沖縄にとって決してよい傾向ではない。この点でも沖縄の新聞社は日本の景気を悪くするのに手をかしているわけだ。
県内新聞の夕刊廃止というのは大きな失態で、市場原理主義の失敗の典型例だと思うが、誰もそれを指摘しない。どうでもいいと思われる存在に成り下がっていたのかも知れない。
25年くらい前までの新聞社の社長達の方がいまよりはるかに責任感が強かったと思う。おかげで当の社長も社員も苦労していたが、いまは「儲からないならやーめた」と気楽なものだ。自分の存在意義を捨てたとしか見えないのだ。
Posted by 渡久地明 at 20:15│Comments(0)
│マスコミ評論