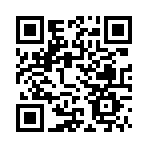2010年11月21日
海治広太郎の沖縄政策
沖縄県知事選挙が盛り下がっているところに、海治広太郎氏から、コメント欄に次の提案を受けた。コメント欄では文字が小さく、もったいないのでわたしがUPし直す。
選挙が「盛り下がっている」というのは伊波陣営が失われた12年を打ち出しているのに公約の中身は仲井眞陣営と似たり寄ったり。失われた12年を取り戻すというなら、全県フリーゾーン、一国2制度をいうべきであるが、全くない。一方の仲井眞陣営は、いままでと同じことをやるといっているだけである。トホホ。
この盛り下がり方は情けない民主党と自民党という2大政党のだらしなさと関連している。両方がバカなことを言うので、沖縄の選挙まで委縮している。そのような退廃ムードを突き抜けた海治広太郎の提言であり、わたしとしては全面的に支持し、このような精神をいまこそ拡大したいと思う。
次の一歩を踏む出そうというなら、下のような熱というか問題意識を踏まえて、もっと挑戦的な論戦を展開して欲しかった。
今のところ沖縄県知事選は、つまらない、退屈な選挙と成り下がっている。投票する人いないんじゃないのか。
選挙が「盛り下がっている」というのは伊波陣営が失われた12年を打ち出しているのに公約の中身は仲井眞陣営と似たり寄ったり。失われた12年を取り戻すというなら、全県フリーゾーン、一国2制度をいうべきであるが、全くない。一方の仲井眞陣営は、いままでと同じことをやるといっているだけである。トホホ。
この盛り下がり方は情けない民主党と自民党という2大政党のだらしなさと関連している。両方がバカなことを言うので、沖縄の選挙まで委縮している。そのような退廃ムードを突き抜けた海治広太郎の提言であり、わたしとしては全面的に支持し、このような精神をいまこそ拡大したいと思う。
次の一歩を踏む出そうというなら、下のような熱というか問題意識を踏まえて、もっと挑戦的な論戦を展開して欲しかった。
今のところ沖縄県知事選は、つまらない、退屈な選挙と成り下がっている。投票する人いないんじゃないのか。
渡久地明
<以下、海治広太郎のメールと提言書>
明さん、ご無沙汰です。
日本独立運動のblog始めました。
http://www.umijikotaro.info/blog
本土のケーブルテレビ会社シアターテレビジョンのネットテレビ部門(ピラニアTV)で沖縄に関する対談をやりました。その広告が月曜日の新報とタイムスの朝刊に載ります。タイトルは、
「今、ネットTVからメディアが変わる!」
「今、沖縄から日本が変わる!」
また、東京にいる沖縄出身の一部有力者が沖縄発の情報発信を支援するために立ち上げたインターネット党という政党のアジア太平洋代表を仰せつかりました。まだ体制が固まっていないので、自分の力量を試す絶好の機会です。既成政党に参加して奴隷になるよりも、新しい政党を立ち上げる方がやりがいがあると思うので、奮ってご参加ください。政策を固めるのに半年ほどかけ、それから組織を急激に拡大するつもりです。
明さんの農業政策はとても優れており、私の農水ラインとつなげたいので、ゆっくり相談しましょう。
我々もいつの間にか、宮城弘岩門下の長老格とも言える年齢になってきたように思います。そろそろ宮城さんの理想の実現に向けて動きたいですね!
私としては、これから沖縄の要求を本土に突きつけるために、少しヤクザ化しなければと思っています。明さん、精神的にバックアップしてください。
あと、島さん(ボリビアにいる島袋正克氏)からお叱りを受けた21世紀戦略メモですが、中央政府への経済要求を前面に打ち出してくれという声が強かったので、基地に触れた部分を経済要求に書き換えた修正版を送ります。
要求の重要な柱は、
1.尖閣諸島周辺の海底資源の試掘・採掘権及びこれに関係する許認可権の沖縄県への権限委譲
2.県内に対する国税(法人税・所得税・相続税・贈与税)の免除
の2本です。
取り上げてもらえると助かります。
戦略メモ修正版
海治広太郎の沖縄21世紀戦略メモ(ver 2.1)
2010.11.15
1.沖縄県固有の資源
A. 沖縄県の歴史的・地理的特異性
B. 県民の独立心と国際的商人(交易)文化
C. 温暖な気候と花粉症フリー
D. 海と平和を願う心
2.資源を生かした振興戦略
A. 沖縄県の歴史的・地理的特異性を今こそプラスに転化し、日本の発展に役立てる
県経済は、1972年の沖縄返還まで米国の施政下にあり、円安と高度経済成長の恩恵を受けられなかったため、工業基盤が弱い。しかも、全国の専用施設の74.7%が集中する米軍基地が、県民の経済活動にとって重要な中南部地域のかなりの部分を占めている。
国税収入: 全国47兆5546億円 沖縄県 2632億円 (0.55%)(H14実績)。
他府県と類似の成長戦略を取れない分、日本の他地域に先駆けて海洋資源開発、観光、貿易、金融の振興に積極的に取り組むことができる。今回の中露の行動からもわかるように、安保・国防、沖縄・北海道振興、領土外交、そして国際的な経済・観光振興・資源開発は相互に密接な関係にあり、政府が地域住民の声に耳を傾け、その主体性を積極的に活用した総合的な戦略を編み出す必要がある。日本人は、沖縄問題に取り組むことで、島国根性から抜け出し、真の意味で国際化し、独立することができる。沖縄県のかかえる問題は、全日本人にとっての試練であると同時に、日本が今後、国際的に発展していくための貴重な試金石である。
B. 独立心と交易文化を生かし、次世代を国際的商人として育成する
政府(通産省)に支援された戦後日本の総合商社)では、もはや多様化した国際市場に浸透することはできない。ユダヤ系や華僑を見習い、商人一人一人の個性と創意工夫を生かせる営業スタイルに転換しなければならない。海外に単身で乗り込み、現地の住民を組織し、販売組織を構築できるオルガナイザーを育てる(ネットワーク展開に切り替える)必要がある。
沖縄県民は、これまでも自営業者として海外の現地社会に溶け込んでビジネスを展開してきた実績があり、今後主流になるビジネス・スタイルでは、縦社会の伝統の強い県外の人々よりも、はるかに高い能力を発揮する。ただし、薩摩侵攻以降、サトウキビを中心とするモノカルチャー経済を強制され、県民が国際的ビジネスのノウハウを失っているため、学習能力の高い青少年を対象に最新の商人教育を施す必要がある。
C. 温暖な気候と花粉症フリーを生かし、国際交流、語学の学習、そしてビジネスに役立てる(観光の視野を国際的に広げることで、多角的なビジネス機会が生まれる)
沖縄の気候は、海洋性気候であるため、相対的に夏は涼しく、冬は温暖だが、低緯度にあるため、夏は比較的高温になる。関東以北の住民にとっての避寒地として特に魅力がある(付加価値が高い)のは冬季だと考える。これまでのような観光リゾートの発想では、設備投資コストがかさむ上に、季節変動が大きいことで年間の稼働率が低く、不況下におけるビジネスモデルとしては成立しない。やはり、これからは、リゾート展開よりも、避暑・避寒地として、富裕層の長期滞在と国際交流を狙った方が客単価も高く、環境負荷が少ないために、県民にとってのメリットが大きい。
また、県民にとっては、沖縄の冬でもかなり寒く感じられるため、緯度による体感温度の差を上手に活用し、県外の避寒客を受け入れた分、県民が沖縄よりもさらに温暖かつ滞在コストの安い東南アジアを避寒地として利用し、その差額を利益として獲得する一方、東南アジアで語学を学び、ビジネスを展開するというモデルを考える必要がある。
逆に沖縄よりも気温の高い東南アジア国民は、一番暑い夏に沖縄を避暑地として利用できる。
・ ターゲット市場
i) 冬の関東以北の住民(特に北海道民)にとっての避寒地
ii) 春と秋の県外住民にとっての花粉症逃避地
iii) 夏の東南アジアの富裕層にとっての避暑地
・ 発想の転換
市場を囲い込むためには、他地域との戦略提携によるパッケージ化や複合展開が必要
- 冬場に県外住民が南下した分、県民は東南アジアに南下して語学を学び、商売をする。
- 夏場の避暑地になる北海道とセットにし、航空会社と組んで「冬は沖縄、夏は北海道」という観念を定着させる。(道民は、サハリンや中国北部に北上し、その期間を語学学習やビジネス展開に充てる)
D.平和を願う心と海を生かし、沖縄を世界平和と共生のシンボルとして発信する
これまでの観光開発は資源浪費型で環境負荷が高く、持続性に欠けていた。「沖縄の海」は、今後、環境保護と平和への強い願いを国際的にアピールするために活用すべきであり、その方が国際的な宣伝効果も高い。沖縄の海を平和と共生のシンボルとしてアピールすることでメッセージ性が高まり、インターネットを利用したコンテンツの制作・配信など、沖縄の海の持続性のある多角的活用が可能になる。
3.初動
A. 政府が沖縄県の試掘・採掘権を認可し、地域主体の国際的開発枠組みを整備する
- 現在問題となっている尖閣諸島は、歴史的にも沖縄県との結びつきが強く、現在も沖縄県石垣市に属する。政府は、歴史的主張に併せて、地元主体の資源開発による実績作りを早急に進める必要がある。尖閣問題の本質が資源問題である以上、日本政府が、まず地元沖縄県の採掘権を認可し、これを土台にして日米共同で国際的開発枠組みを構築し、その上で中国・台湾の資本を誘致するという積極策を積み重ねる以外、この問題を解決する道はない。
B. 県民の独立心と国際的商人(交易)文化を生かす
- 商人としての基礎的訓練として、青年たちに行商をさせる。批判は多いものの、現代の行商システムとしては、無店舗販売システムが優れている(公費を使わずに教育できる)。米国に展開するにはオンライン・ビジネスが有利である。まず、それぞれの地元で営業させ、成績優秀者を本土に送り込み、本土での成績優秀者に短期集中的な語学訓練を施し、米国に送り込む。米国に送り込まれたスタッフがA.の活動を支援するのと引き換えに、活動を支援する。
C. 温暖な気候と花粉症フリーを生かす
- 観光庁がとりまとめ役となり、国内は沖縄と北海道が中心になり、ロシア、中国、米国、南米、東南アジアなどの国々とタイアップし、観光協定を結び、共同基金を設置し、観光振興を図る(観光外交の積極的展開)。
D. 海と平和を願う心を生かす
- 行政が中心になって平和運動と海洋環境保護運動に取り組む(ハリウッドと連携して映画を制作するなど)。
4.最終目標
A. 沖縄を環太平洋の経済・金融・観光のセンターに発展させることで、県民所得を日本最高水準に引き上げ、完全失業率を全国最低水準に引き下げ、沖縄が日本経済の牽引役として日本の経済成長に大きく貢献する。
B. 既存のシステムを利用して販売ネットワークを形成、市場を確保した後に(二段ロケット戦略)ネットワーク型の総合商社を沖縄に設立し、世界有数の財閥に育てる。
C. 長期滞在型交流システムによって県民と環太平洋諸国民との大規模な交流を進め、沖縄の支持者を増やすと同時に、環太平洋連邦を推進し、その枠組みの中で、沖縄と台湾の平和を実現する。
D. 日米地位協定をドイツ並みに見直し、粘り強い運動を積み重ねる中で、沖縄が世界平和と環境保護のシンボルになる。
5.以上の構想が実現するための条件 - 沖縄を起爆剤とする日本の政界再編
I. 県知事選を契機とする県民の大同団結とインターネットによる世界に向けた情報発信
II. 一国二制度の導入による全県フリーゾーン化と、国税(法人税、所得税、相続税、贈与税)の免除。世界最低の税率によって世界から人と企業と資金を流入させる。
III. タックスヘブン効果による人と企業の流入に伴う観光産業の活性化(観光客の3倍増)
IV. 沖縄のエネルギーの本土波及とインターネット選挙による政界再編及び救国政権の形成
V. 沖縄が旗を振り、日本国民の総力を結集した外交交渉と環太平洋連邦運動を推進する。
Marcelo Umiji
Posted by 渡久地明 at 16:04│Comments(0)
│琉球の風(区別不能の原稿)