2012年12月24日
「家計に届く景気回復」(沖縄タイムスの社説)とは
今日の沖縄タイムス社説「アベノミクス始動/家計に届く景気回復」(2012年12月24日)が面白い。タイトルは素晴らしい。わたしもそう思う。で、読んでみると、トホホな内容。ま、社説なんか読む人は少ないと思うが、けなしたりくさしたりする材料としてはちょうどよい。公平を期すために全部コピペしながら解説しよう。
(1)前半は用語の解説であまり問題はないだろう。支持も批判めいた様子もない。ところが次。
(2)法律で独立性を保障されたという部分は、98年頃からの今の法律がそうなっているわけだが、それがおかしいという批判が最近急速に高まっているのである。中央銀行の独立性には、目標設定の独立性と目的達成のための手段の独立性の二つがあって、諸外国では景気を良くする、雇用を最大化するという政府と中央銀行共通の目的があり、中央銀行は独立の金融政策で目標を達成する、目標達成の手段の独立性が保障されているというのが、当たり前になっている。
これはそうだろう、もし日銀が楽をしたいのなら、低い目標を自分で決めて、それの達成もチンタラやればいいというしょうもない結果になる。15年デフレの原因は日銀の消極姿勢が問題だったということが、いま問題になっているのだ。世界の中央銀行が2〜4%のインフレ目標を設定しているのに、日銀は今年のバレンタインデーの1%のインフレめど、実現は2014年以降というバカな目標を自分で決めて、2年も3年も成り行きを待つという姿勢なのがダメなのである。
それに対して、2〜3%のインタゲを設定すると安倍総裁が発言しただけで、円安・株高に市場が動いた。まさに円安・株高はデフレ脱却の前兆であり、日銀のインめどよりはるかに効果があったわけだ。首相就任後はこれを徹底してやる予定である。
そこに「日銀=被害者」と単純に」決めつけることはできないと社説はいう。被害者のところは加害者の誤字かと思ったら、そうではないようなのでびっくりだ。上に述べたような事情を社説子は全くわかっていないらしいぞ…。
(3)大規模な財政出動は十分な成果を上げたとはいえないというが、実はそれがなかったら日本発世界恐慌となっていたのを、財政出動で防いだ可能性があるのだ。景気回復しなかったのは、規模が小さすぎたからだ。かつ、日銀は財政政策に全く協力しなかったという前科がある。
国債発行残高をふくらませ、大きな副作用を生むと言っているが、現状の不況より大きな副作用とはなんだろうか。最悪の現状から抜けだ
そうというまともな考えのどこに問題があるのだろうか。アベノミックスは何も安倍総裁のオリジナルの政策ではない。金融と財政の組み合わせで不況を脱出せよという政策は1929年にも行われたし、最近の世界同時不況で世界中で取られている政策でもある。そしてそれらは成功しつつある(まだ規模が足りないが)。日本が大きく不況を抜けだしてふたたび力強く成長し始めれば、国際的にも良い影響が出てくる可能性が高いのだ。
(4)小泉政権の新自由主義とは全く反対のことを行う、これまでの自民党の政策とは異なる次元の政策というのが安倍総裁の主張である。同じ事をやるバカはいない。同じと決めつける社説子のほうがおかしい。意味がわかっていないのだろう。
最後の結論部分はまさにそれを公共事業を通じてやろうとしているのがアベノミクスだといえる。公共事業で幅広い分野にカネを行き渡らせ、幅広く消費や投資を換気しようというものだ。景気回復で強い国家を取り戻そうといっている。しかし、公共事業ではすべての家計に恩恵が行き渡るにはやや時間がかかりそうだ。そこで私としては、国民全部にカネを配るのがよいと思っている。
実際に家計を豊にするには公共事業より、国民に直接カネを配るのが早い。だから欧米では財政出動といえば減税政策が中心となる。
公共事業はせいぜい年間20〜30兆円しか実行できない可能性がある(土木建築業界に工事をこなす能力がない)が、国民一人ひとりに100万円バラ撒けば、その半分でも消費されることで、あらゆる分野で生産が増え、仕事が増え、雇用が拡大、所得も増え、さらに消費を産んで景気回復となる。政府がカネを使うのでなく、国民がカネを使って景気を回復させるわけだ。家計を豊にするためには、こういう解決の手法があるのだから、社説子はそれを主張すべきだろう。
もっとも、このやり方は公共事業よりも法律を通すのが難しいかもしれない。しかたがないので公共事業中心ということになるのだが、西日本大震災に備えての国土強靭化、都市機能の分散は確かに差し迫った問題であり、早くやるべきだ。減税も組み合わせるともっとよい。
追記:レーガノミクスはインフレ下で供給サイドを強化し、通貨供給量を絞る経済政策。安倍総裁の政策とは180度異なる。わかりやすいために、京都大学の先生たちがまとめた(中野剛志や藤井聡がよく使う)下の表を参照。

政権発足を待たず、早くも「アベノミクス」が本格始動した。デフレ脱却を最優先課題に掲げる安倍自民党が衆院選に圧勝したことで、市場では円安・株高が進み、景気回復への期待感が急速に高まっている。
「アベノミクス」は、安倍晋三自民党総裁のアベと、経済を意味するエコノミクスを合成した造語で、安倍新政権の経済政策のことを指す。
安倍総裁は、衆院選直後の18日、日銀の白川方明総裁に会い、「2%の物価目標(インフレターゲット)に向けて日銀と政策協定を結びたい」とインフレ目標の導入を求めた。物価上昇率を前年比2%とするインフレ目標を設定するよう、日銀法の改正までちらつかせながら、先制パンチを放ったのである。
日銀は20日の金融政策決定会合で、10兆円の追加金融緩和に踏み切るとともに、物価目標の導入についても来年1月に結論を出すことを決めた。自民党の申し入れを受け入れる意向だ。
(1)前半は用語の解説であまり問題はないだろう。支持も批判めいた様子もない。ところが次。
法律で金融政策の独立性を保障された日銀は、政治の圧力にいとも簡単に屈したことになる。消極的だった日銀が方針を急転換したのは、自公が衆院で3分の2を超える議席を獲得したからだ。
政治介入は避けるべきだが、「日銀=被害者」と単純に決めつけることはできない。日銀は、デフレ脱却の有効打を打ち出せず、経済の停滞を招いた結果責任の一端を免れないのである。選挙で示された「民意」と、長引くデフレが、日銀に大転換を迫った、と見るべきだろう。
(2)法律で独立性を保障されたという部分は、98年頃からの今の法律がそうなっているわけだが、それがおかしいという批判が最近急速に高まっているのである。中央銀行の独立性には、目標設定の独立性と目的達成のための手段の独立性の二つがあって、諸外国では景気を良くする、雇用を最大化するという政府と中央銀行共通の目的があり、中央銀行は独立の金融政策で目標を達成する、目標達成の手段の独立性が保障されているというのが、当たり前になっている。
これはそうだろう、もし日銀が楽をしたいのなら、低い目標を自分で決めて、それの達成もチンタラやればいいというしょうもない結果になる。15年デフレの原因は日銀の消極姿勢が問題だったということが、いま問題になっているのだ。世界の中央銀行が2〜4%のインフレ目標を設定しているのに、日銀は今年のバレンタインデーの1%のインフレめど、実現は2014年以降というバカな目標を自分で決めて、2年も3年も成り行きを待つという姿勢なのがダメなのである。
それに対して、2〜3%のインタゲを設定すると安倍総裁が発言しただけで、円安・株高に市場が動いた。まさに円安・株高はデフレ脱却の前兆であり、日銀のインめどよりはるかに効果があったわけだ。首相就任後はこれを徹底してやる予定である。
そこに「日銀=被害者」と単純に」決めつけることはできないと社説はいう。被害者のところは加害者の誤字かと思ったら、そうではないようなのでびっくりだ。上に述べたような事情を社説子は全くわかっていないらしいぞ…。
自民、公明両党は、10兆円規模の大型補正予算を編成する方針だ。自民党は選挙公約で、事前防災を重視した国土強靱(きょうじん)化政策を掲げ、公共投資の拡充を打ち出した。
大規模災害に備え防災・減災対策を強化するのは理解できる。しかし、これにも落とし穴があって、必要性や内容を十分に吟味せず、「総額ありき」で話が進むと、無駄な事業が山を成す恐れがある。
大規模な財政出動による景気の底上げは、自民党政権時代に何度も試みられた手法だが、十分な成果を上げたとはいえない。
安倍総裁は金融政策、財政政策、成長戦略の三本柱を組み合わせて経済を立て直していく考えだが、ベストミックスが実現しなければ、国債発行残高を膨らませ、大きな副作用を生むことを覚悟しなければならない。
(3)大規模な財政出動は十分な成果を上げたとはいえないというが、実はそれがなかったら日本発世界恐慌となっていたのを、財政出動で防いだ可能性があるのだ。景気回復しなかったのは、規模が小さすぎたからだ。かつ、日銀は財政政策に全く協力しなかったという前科がある。
国債発行残高をふくらませ、大きな副作用を生むと言っているが、現状の不況より大きな副作用とはなんだろうか。最悪の現状から抜けだ
そうというまともな考えのどこに問題があるのだろうか。アベノミックスは何も安倍総裁のオリジナルの政策ではない。金融と財政の組み合わせで不況を脱出せよという政策は1929年にも行われたし、最近の世界同時不況で世界中で取られている政策でもある。そしてそれらは成功しつつある(まだ規模が足りないが)。日本が大きく不況を抜けだしてふたたび力強く成長し始めれば、国際的にも良い影響が出てくる可能性が高いのだ。
1980年代初め、レーガン米大統領が打ち出した「レーガノミクス」は、結果的に財政赤字を拡大させた。小泉純一郎政権時代に取り組んだ新自由主義政策も、庶民のフトコロを暖かくしたわけではなかった。
「富める者が富めば、貧しい者にも富が浸透(トリクルダウン)する」というトリクルダウン理論に基づく政策で潤ったのは、一部の企業と富裕層だけであった。
雇用を拡大し、各層に広がる貧困化を食い止めること。家計が豊かになるような、庶民目線の経済政策を打ち出すこと。そのような経済政策を多くの有権者が求めている。
(4)小泉政権の新自由主義とは全く反対のことを行う、これまでの自民党の政策とは異なる次元の政策というのが安倍総裁の主張である。同じ事をやるバカはいない。同じと決めつける社説子のほうがおかしい。意味がわかっていないのだろう。
最後の結論部分はまさにそれを公共事業を通じてやろうとしているのがアベノミクスだといえる。公共事業で幅広い分野にカネを行き渡らせ、幅広く消費や投資を換気しようというものだ。景気回復で強い国家を取り戻そうといっている。しかし、公共事業ではすべての家計に恩恵が行き渡るにはやや時間がかかりそうだ。そこで私としては、国民全部にカネを配るのがよいと思っている。
実際に家計を豊にするには公共事業より、国民に直接カネを配るのが早い。だから欧米では財政出動といえば減税政策が中心となる。
公共事業はせいぜい年間20〜30兆円しか実行できない可能性がある(土木建築業界に工事をこなす能力がない)が、国民一人ひとりに100万円バラ撒けば、その半分でも消費されることで、あらゆる分野で生産が増え、仕事が増え、雇用が拡大、所得も増え、さらに消費を産んで景気回復となる。政府がカネを使うのでなく、国民がカネを使って景気を回復させるわけだ。家計を豊にするためには、こういう解決の手法があるのだから、社説子はそれを主張すべきだろう。
もっとも、このやり方は公共事業よりも法律を通すのが難しいかもしれない。しかたがないので公共事業中心ということになるのだが、西日本大震災に備えての国土強靭化、都市機能の分散は確かに差し迫った問題であり、早くやるべきだ。減税も組み合わせるともっとよい。
追記:レーガノミクスはインフレ下で供給サイドを強化し、通貨供給量を絞る経済政策。安倍総裁の政策とは180度異なる。わかりやすいために、京都大学の先生たちがまとめた(中野剛志や藤井聡がよく使う)下の表を参照。

Posted by 渡久地明 at 10:55│Comments(0)
│デフレ脱却
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|















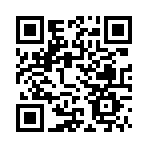
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。