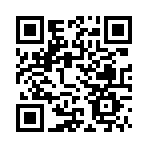2005年04月15日
価格が安いのは需要が足りないから
観光客は増えているのに売上が上がらないという傾向は過去何度か
あった。
80年代前半には価格競争が激化して、この時も二泊三日2万9,800円の
ツアーが話題になった。
この時は、価格競争が起こったにもかかわらず、観光客数はそれほど
増えなかった。
90年代前半のホテル界業ラッシュでも同じことが起こっている。
続々新設ホテルがオープンしたが、湾岸戦争のあとの超円高で
海外旅行人気が高まり、沖縄は伸び悩んだ。
再び価格競争が起こる。
最近も同じ傾向にあり、県内日刊紙は観光産業は生産性が低いとか、
豊作貧乏と書き立てている。
表面的にはそのように見えるが、実際には何がそうさせているのだろう。
まず、低価格商品が話題になるが、これは日本人の観光の時期に
季節変動があるのでピーク時に高くなり、オフ期に安くなるのは
需要と供給の経済学が示す通りの当たり前の現象である。
季節変動があるのでピーク時に高くなり、オフ期に安くなるのは
需要と供給の経済学が示す通りの当たり前の現象である。
需要が少ないときには価格を下げ、需要を喚起しなければならない。
一方、需要が旺盛な夏場は供給が追いつかない分、価格を上げて
需要を制限しているわけだ。
需要を制限しているわけだ。
だから、いま客室料金が5,000円で安すぎるというのは表面的なものの
見方にすぎない。
見方にすぎない。
これに対してビジネスホテルが年中一定価格で例えば六千円の室料を
設定している。
設定している。
つまり、六千円の客室なのである。
ところが総合ホテルは最初から一万五千円の客室をつくってあり、
オフ期には五千円に下がっているだけだから、客室のグレードは
ビジネスホテルよりはるかに高い。
オフ期には五千円に下がっているだけだから、客室のグレードは
ビジネスホテルよりはるかに高い。
宿泊客にとって相当な割安感があることになる。
これを区別しないで豊作貧乏と決めつけるのは間違いだろう。
また、総合ホテルは内容を説明した上で価格を提示した方がよい。
ネット販売での価格競争で、価格だけで勝負してはいけないと思う。
より本質的には、オフの需要を喚起することによって5,000円の客室を
6,000円、7,000円で売れるようにすることを考えるべきだ。
6,000円、7,000円で売れるようにすることを考えるべきだ。
20年前の観光業界はこの当たり前の政策で動いていたが、最近は
ヘンである。
ヘンである。
とにかくオフ期だから価格を下げるという形式的な価格設定になっている
ように見える。
ように見える。
経験者がだんだんいなくなってきたのだと思う。
もっと奧には日本のデフレの影響がある。
構造改革で公共工事が沖縄でも激減しているが、少なくとも前年より
1、2%でも増えているという政策がとられていれば、観光産業の売上は
そのまま県民所得の底上げにつながっていたはずである。
いまの状態は公共工事が減った分を観光産業が穴埋めして
全体としてプラスマイナスゼロか、わずかなプラスでしかない。
全体としてプラスマイナスゼロか、わずかなプラスでしかない。
失業率は改善せず、県民所得も低いままで構造だけ変わる
ということになる。
美しい国土をつくるための優れた土木・建築技術の継承が
出来ず、生産性は毀損される。
フタを開けてみれば観光産業のエキスパートもどんどんいなくなり、
かえって産業全体が衰退の方向に向かうことになる。
かえって産業全体が衰退の方向に向かうことになる。
Posted by 渡久地明 at 15:21│Comments(0)
│琉球の風(区別不能の原稿)