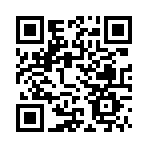2005年04月29日
経済学は面白い
大学で電気・電子工学を学んだが、電気の本流というのは
当時は
電磁気、半導体(物性)、電気・電子回路、気体電子
というところだろうと思っていた。
コンピュータはあったが、軟弱な分野だと思われていた。
ところが、最近は電気・電子工学が情報工学に吸収されて学科そのものがなくなっているというケースが珍しくないようだ。
で、電気の中でも高電圧とか、高エネルギーを扱うものがかっこいいと思っていた。この分野の先には核融合とか素粒子が見える。
おかげで経済とか社会、政治、法律などのいわゆる文系の知識がわたしの頭の中からまるっきり抜け落ちており、仕事を通じて得られたものをあとで文献などで裏付けるということをしている。
経済についてはまるっきり勉強しようという気が起こらず長い間ほったらかしにしていた。ところが、構造改革がでてきてからどうしても納得できない疑問がどんどんでてきた。例えば、郵便局を民営化したら景気は良くなるのだろうか。全く関係がないはずだということは合理的に予想できるが、経済学ではそうではないのか? 問題を考えるヒントはインターネットの掲示板にあった。2ちゃんねる経済板はよく見ている。
面白いと思った。科学であると思う。数学も高度なものを使う人がいる。そうではないだろうという先入観があって、敬遠してきたのだった。しかし、この考えは間違いであることにすぐに気が付いた。
いくつかの経済現象はまるで電気回路のような動きをしており、特に本業である沖縄の観光客数の推移はかなりきれいな自然現象のようにふるまっている。これを説明する学問は電気の理論かも知れないし、すでに経済学者が研究しているかも知れない。今のところ経済学者(観光学者も)が沖縄の観光客の伸びに合理的な説明をしたという話しは聞かないので、わたしの理論は随分先をいっている可能性がある。
構造改革がきっかけで経済学をのぞいてみたら、意外に面白い。わたしは数学はお手のものである(だいぶ忘れたが使い方を知っている)。工学部の発想でいくつかのテーマにチャレンジしてみようと思う。経済学の理解には工学部での実験や数学の使い方の経験や理解は大いにプラスであるとさえ思う。
当時は
電磁気、半導体(物性)、電気・電子回路、気体電子
というところだろうと思っていた。
コンピュータはあったが、軟弱な分野だと思われていた。
ところが、最近は電気・電子工学が情報工学に吸収されて学科そのものがなくなっているというケースが珍しくないようだ。
で、電気の中でも高電圧とか、高エネルギーを扱うものがかっこいいと思っていた。この分野の先には核融合とか素粒子が見える。
おかげで経済とか社会、政治、法律などのいわゆる文系の知識がわたしの頭の中からまるっきり抜け落ちており、仕事を通じて得られたものをあとで文献などで裏付けるということをしている。
経済についてはまるっきり勉強しようという気が起こらず長い間ほったらかしにしていた。ところが、構造改革がでてきてからどうしても納得できない疑問がどんどんでてきた。例えば、郵便局を民営化したら景気は良くなるのだろうか。全く関係がないはずだということは合理的に予想できるが、経済学ではそうではないのか? 問題を考えるヒントはインターネットの掲示板にあった。2ちゃんねる経済板はよく見ている。
面白いと思った。科学であると思う。数学も高度なものを使う人がいる。そうではないだろうという先入観があって、敬遠してきたのだった。しかし、この考えは間違いであることにすぐに気が付いた。
いくつかの経済現象はまるで電気回路のような動きをしており、特に本業である沖縄の観光客数の推移はかなりきれいな自然現象のようにふるまっている。これを説明する学問は電気の理論かも知れないし、すでに経済学者が研究しているかも知れない。今のところ経済学者(観光学者も)が沖縄の観光客の伸びに合理的な説明をしたという話しは聞かないので、わたしの理論は随分先をいっている可能性がある。
構造改革がきっかけで経済学をのぞいてみたら、意外に面白い。わたしは数学はお手のものである(だいぶ忘れたが使い方を知っている)。工学部の発想でいくつかのテーマにチャレンジしてみようと思う。経済学の理解には工学部での実験や数学の使い方の経験や理解は大いにプラスであるとさえ思う。
Posted by 渡久地明 at 20:12│Comments(0)
│デフレ脱却