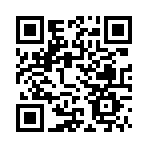2005年10月04日
なぜ、辺野古浅瀬なんだろう。
以下は、沖縄問題が日米を揺るがしていた頃の97年、沖縄の過重負担を減らそうという議論の米側の考え。(下線はわたし。以下同じ。このレポートを読んで、アメリカと話ができそうだと思い、別件の調査チームに潜り込んでアメリカ取材を計画したところ、アーミテージが会うといっていると沖縄の米領事館から連絡を受けた。このレポートを書いた人に会いたいと領事館に申し入れたのだった。本人が出てくるとは思わなかった。99年暮れ、ワシントンでアーミテージは「沖縄基地に長居はしない。アジアが安定したら出ていく」とわれわれ沖縄からの調査チームに述べた(詳細はhttp://www.sokuhou.co.jp/backno/560.html#t1)。なお、このCFRレポートはWebでも公開されていたが、最近リンク切れになっているようだ)
============
(略)
安保関係は、同盟体制における政治的権限と軍事的責任をめぐる不均衡・非対称性を低下させることで強化できる。その場合、日本は集団的自衛権を否定する解釈を放棄し、地域的な緊急事態における支援体制を正当な自衛権の解釈に含める。こうして日本は、起こりうる軍事紛争の対応計画に「想定され」、自衛隊は米軍とより緊密に協力する。ひきかえに日本は、日米安全保障体制のなかでアジアの軍事危機に日米の軍隊が関与する際の政治的決定により大きな発言権を持つ。そうなれば、沖縄の基地問題も、防衛庁と国防総省との長期的な協力構想の枠組みのなかで扱うことができるようになる。
(略)
(1997年、米外交問題評議会タスクフォースリポート「日米安全保障同盟への提言」リチャード・L・アーミテージ 共同議長、ハロルド・ブラウン 共同議長(c) 1997 by the Council on Foreign Relations, Inc. & Foreign Affairs, Japan.)
============
その後の日本。「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成16年12月10日、閣議決定)のある部分を取り出すと。
============
(略)
安保関係は、同盟体制における政治的権限と軍事的責任をめぐる不均衡・非対称性を低下させることで強化できる。その場合、日本は集団的自衛権を否定する解釈を放棄し、地域的な緊急事態における支援体制を正当な自衛権の解釈に含める。こうして日本は、起こりうる軍事紛争の対応計画に「想定され」、自衛隊は米軍とより緊密に協力する。ひきかえに日本は、日米安全保障体制のなかでアジアの軍事危機に日米の軍隊が関与する際の政治的決定により大きな発言権を持つ。そうなれば、沖縄の基地問題も、防衛庁と国防総省との長期的な協力構想の枠組みのなかで扱うことができるようになる。
(略)
(1997年、米外交問題評議会タスクフォースリポート「日米安全保障同盟への提言」リチャード・L・アーミテージ 共同議長、ハロルド・ブラウン 共同議長(c) 1997 by the Council on Foreign Relations, Inc. & Foreign Affairs, Japan.)
============
その後の日本。「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成16年12月10日、閣議決定)のある部分を取り出すと。
============
(略)
3 日米安全保障体制
米国との安全保障体制は、我が国の安全確保にとって必要不可欠なものであり、また、米国の軍事的プレゼンスは、依然として不透明・不確実な要素が存在するアジア太平洋地域の平和と安定を維持するために不可欠である。
さらに、このような日米安全保障体制を基調とする日米両国間の緊密な協力関係は、テロや弾道ミサイル等の新たな脅威や多様な事態の予防や対応のための国際的取組を効果的に進める上でも重要な役割を果たしている。
こうした観点から、我が国としては、新たな安全保障環境とその下における戦略目標に関する日米の認識の共通性を高めつつ、日米の役割分担や在日米軍の兵力構成を含む軍事態勢等の安全保障全般に関する米国との戦略的な対話に主体的に取り組む。その際、米軍の抑止力を維持しつつ、在日米軍施設・区域に係る過重な負担軽減に留意する。
(略)
(http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/17taikou/taikou.htm)
============
これまで、米国の言うとおりに日米同盟が強化されてきたと見て良いと思うが、97年のCFRレポートと04年暮れの防衛大綱にかなりの温度差がある。防衛大綱は米の言い分を薄めてある(しかし、似ている)。
米はハッキリ「集団的自衛権の行使」を日本が認め、それによって自衛隊が起こりうる軍事紛争の対応計画に「想定される」ようになれば、結果として沖縄の負担軽減ができると当時はいっていたのであり、辺野古沖の基地ができる、できないは表面的な話で、これが主要な問題ではないだろう。
00年10月のアーミテージ・レポート(「米国と日本—成熟したパートナーシップに向けて」)は沖縄の負担軽減の意味をさらに詳しく述べ、SACO合意よりももっと踏み込めといっている。一方で米軍の分散を図ることによって、永続的なプレゼンスを確保できるとしている。97年のレポートよりも強力に沖縄基地の削減を力説している。自民党の総裁選を意識したものかも知れない。翌01年4月に小泉内閣が誕生する。また、最近の辺野古に関する米側の言い分も、この線に近いだろう。沖縄の章を全部引用しよう。これはネットに訳がある。
============
Okinawa (沖縄)
在日米軍の約75%が沖縄に集中している。これは安全保障上と、もう一つ距離上の理由からである。沖縄は東シナ海と太平洋が接する場所に位置し、韓国・台湾・南シナ海へ飛行機でたった1時間だ。
米空軍嘉手納基地は、地域の戦力投射の要といえる位置にある。日本防衛でも重要な役割を果たす。沖縄駐屯の第3海兵隊遠征軍は自力作戦能力をもつ前方展開/即応部隊であり、非戦闘員救出作戦から侵略者を叩く最新戦力の大型作戦までやれる。
しかし、米戦力の過密集中は沖縄県民にとって大きな負担になっているし、米軍にとっても演習の制約などの問題がある。作戦テンポが濃密なことや隊員が若いことから、海兵隊は日本国民から特殊な目で見られ、日本人は最南端の沖縄県における米軍のプレゼンスの変更を望んでいる。
米海兵隊はよき隣人たるべく努力を重ねてきたが、基地の周辺の人口急増によって即応態勢や訓練への支障が増えつつある。米兵の非行事件は統計的には急減しているが、今の政治風土下で、不幸にも発生した事件への関心は過度に大きくなる。
1996年、SACO協定によって在沖米軍基地の再編・統合・削減が求められた。日米両国はその協定を実施することになっており、削減は普天間飛行場も含めて5000ヘクタール、11施設にたちする。
我々はSACO協定が第4の大事な目標を盛り込むべきであったと思う。アジア太平洋地域における(米軍基地の)分散化である。軍事的見地からすれば、米軍が地域全体で広範かつ柔軟なアクセスを確保することは非常に重要であり、一方政治的見地からすれば沖縄県民の負担を軽くすることが不可欠である。そうすることによって、永続的で信頼できるプレゼンスを確保できるのである。日本における米軍の戦力構造に関する検討はSACO協定の段階でとどめてはならない。米政府は、アジア全体を通じて海兵隊のもっと広範で柔軟な展開と訓練のオプションを考えるべきである。
(http://www.sys-tems.co.jp/nexus/attntion/arm_0010.htm)
============
このレポートの後の01年、911テロが起こる。これで、沖縄の取扱が変更になっただろうか。テロ後、来沖したロビン・サコダ氏(アーミテージの子分。来沖時には国防総省に復帰していた)にテロでアーミテージレポートの内容に変更があるかと聞いたら、明快に「ない」と応えた。
米は沖縄基地の無条件返還も確かに考えていたと思わせる報道がいくつかあった。今年3月には辺野古断念、那覇軍港、キャンプキンザー、普天間基地も返すという日本「政府筋」からのリークもあり、県内経済界を驚かせたものだ(6月頃に新聞記事にもなった)。
すんなり、返還もあり得るという環境ができていて、オーストラリア、グアム、ハワイ、フィリピンなどでの米軍の訓練移転が日・米・豪の新聞で報じられてきた。ここにきてなぜ、辺野古浅瀬なのだろうというのが、わたしの疑問。
以上の文章は日米文書とわたし自身の取材に基づく推理であり、軍事的な知識は全然含まれていない。
(略)
3 日米安全保障体制
米国との安全保障体制は、我が国の安全確保にとって必要不可欠なものであり、また、米国の軍事的プレゼンスは、依然として不透明・不確実な要素が存在するアジア太平洋地域の平和と安定を維持するために不可欠である。
さらに、このような日米安全保障体制を基調とする日米両国間の緊密な協力関係は、テロや弾道ミサイル等の新たな脅威や多様な事態の予防や対応のための国際的取組を効果的に進める上でも重要な役割を果たしている。
こうした観点から、我が国としては、新たな安全保障環境とその下における戦略目標に関する日米の認識の共通性を高めつつ、日米の役割分担や在日米軍の兵力構成を含む軍事態勢等の安全保障全般に関する米国との戦略的な対話に主体的に取り組む。その際、米軍の抑止力を維持しつつ、在日米軍施設・区域に係る過重な負担軽減に留意する。
(略)
(http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/17taikou/taikou.htm)
============
これまで、米国の言うとおりに日米同盟が強化されてきたと見て良いと思うが、97年のCFRレポートと04年暮れの防衛大綱にかなりの温度差がある。防衛大綱は米の言い分を薄めてある(しかし、似ている)。
米はハッキリ「集団的自衛権の行使」を日本が認め、それによって自衛隊が起こりうる軍事紛争の対応計画に「想定される」ようになれば、結果として沖縄の負担軽減ができると当時はいっていたのであり、辺野古沖の基地ができる、できないは表面的な話で、これが主要な問題ではないだろう。
00年10月のアーミテージ・レポート(「米国と日本—成熟したパートナーシップに向けて」)は沖縄の負担軽減の意味をさらに詳しく述べ、SACO合意よりももっと踏み込めといっている。一方で米軍の分散を図ることによって、永続的なプレゼンスを確保できるとしている。97年のレポートよりも強力に沖縄基地の削減を力説している。自民党の総裁選を意識したものかも知れない。翌01年4月に小泉内閣が誕生する。また、最近の辺野古に関する米側の言い分も、この線に近いだろう。沖縄の章を全部引用しよう。これはネットに訳がある。
============
Okinawa (沖縄)
在日米軍の約75%が沖縄に集中している。これは安全保障上と、もう一つ距離上の理由からである。沖縄は東シナ海と太平洋が接する場所に位置し、韓国・台湾・南シナ海へ飛行機でたった1時間だ。
米空軍嘉手納基地は、地域の戦力投射の要といえる位置にある。日本防衛でも重要な役割を果たす。沖縄駐屯の第3海兵隊遠征軍は自力作戦能力をもつ前方展開/即応部隊であり、非戦闘員救出作戦から侵略者を叩く最新戦力の大型作戦までやれる。
しかし、米戦力の過密集中は沖縄県民にとって大きな負担になっているし、米軍にとっても演習の制約などの問題がある。作戦テンポが濃密なことや隊員が若いことから、海兵隊は日本国民から特殊な目で見られ、日本人は最南端の沖縄県における米軍のプレゼンスの変更を望んでいる。
米海兵隊はよき隣人たるべく努力を重ねてきたが、基地の周辺の人口急増によって即応態勢や訓練への支障が増えつつある。米兵の非行事件は統計的には急減しているが、今の政治風土下で、不幸にも発生した事件への関心は過度に大きくなる。
1996年、SACO協定によって在沖米軍基地の再編・統合・削減が求められた。日米両国はその協定を実施することになっており、削減は普天間飛行場も含めて5000ヘクタール、11施設にたちする。
我々はSACO協定が第4の大事な目標を盛り込むべきであったと思う。アジア太平洋地域における(米軍基地の)分散化である。軍事的見地からすれば、米軍が地域全体で広範かつ柔軟なアクセスを確保することは非常に重要であり、一方政治的見地からすれば沖縄県民の負担を軽くすることが不可欠である。そうすることによって、永続的で信頼できるプレゼンスを確保できるのである。日本における米軍の戦力構造に関する検討はSACO協定の段階でとどめてはならない。米政府は、アジア全体を通じて海兵隊のもっと広範で柔軟な展開と訓練のオプションを考えるべきである。
(http://www.sys-tems.co.jp/nexus/attntion/arm_0010.htm)
============
このレポートの後の01年、911テロが起こる。これで、沖縄の取扱が変更になっただろうか。テロ後、来沖したロビン・サコダ氏(アーミテージの子分。来沖時には国防総省に復帰していた)にテロでアーミテージレポートの内容に変更があるかと聞いたら、明快に「ない」と応えた。
米は沖縄基地の無条件返還も確かに考えていたと思わせる報道がいくつかあった。今年3月には辺野古断念、那覇軍港、キャンプキンザー、普天間基地も返すという日本「政府筋」からのリークもあり、県内経済界を驚かせたものだ(6月頃に新聞記事にもなった)。
すんなり、返還もあり得るという環境ができていて、オーストラリア、グアム、ハワイ、フィリピンなどでの米軍の訓練移転が日・米・豪の新聞で報じられてきた。ここにきてなぜ、辺野古浅瀬なのだろうというのが、わたしの疑問。
以上の文章は日米文書とわたし自身の取材に基づく推理であり、軍事的な知識は全然含まれていない。
Posted by 渡久地明 at 22:07│Comments(0)
│返還基地の跡利用