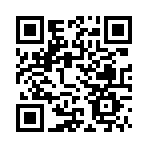2006年01月24日
構造改革とITバブル
ライブドア社長逮捕の報道を見ていると、マスコミの鈴木宗男叩きを思い出す。現時点でのわたしのメモ。
ライブドアについては「ホリエモンの錬金術」
http://blog.goo.ne.jp/yamane_osamu/e/d00aeb354cc4401b60aa87e8569760ad
が早くから、でたらめぶりを指摘していた。
一方で、「小泉の波立ち」
http://www005.upp.so-net.ne.jp/greentree/koizumi/main.htm
は、この程度の帳簿操作などどうってことない、もっと悪いのは小泉だ、といっている。
どちらかが間違っているのではなく、両立していると思う。
その上で、なぜ、このような事件が起こるのかだ。
ホリエモンがライブドアの前身、オン・ザ・エッジをつくったのが1996年。前年の95年がインターネット元年と呼ばれた時期で、わたしも95年暮れにはホームページをつくっていた。そのころ県内にはまだホームページは100もない頃で、ヤフーから電話がかかってきて、掲載しても良いか、許可を求めてきた時期でもある。
世の中はといえば、バブル崩壊で、価格破壊というフレーズが連日叫ばれた。円高で海外旅行が急拡大し、沖縄観光は危機的な状況となっていた。沖縄旅行より海外の方が安いし、サービスも良い、といわれた。しかし、バブル期に客室不足となっていた沖縄では、94年までに大型ホテルが続々開業したため、沖縄全体の稼働率が急激に低下し、危機を迎える。
政府の無駄遣いが連日問題となり、行政改革、金融ビッグバン、省庁再編などが実行された。公務員叩きがくり返され、不況の原因は官僚による無駄な公共投資が原因であるとされた。
日米関係ではポスト冷戦で、日米同盟はいらなくなったのではないか、という議論がある一方、湾岸戦争で日本がもたついたことから、同盟強化に向けて米国の圧力が高まった。
世の中には「日本経済に右肩上がりはあり得ない。少子・成熟社会ではこれまでのような高成長は望めず、GDP成長率はせいぜい2、3%」という迷信が広まった。政府は財政赤字を縮小するために、行・財政改革を優先し、規制緩和を打ち出し、97年、橋本政権下で累進課税を緩和、消費税を3%から5%に拡大する。銀行やゼネコンの経営が破綻し、公的資金がどんどん注入されていった。
社会には不満が充満し、閉塞感という言葉も流行った。不況が5年も続き、今後も景気は良くなりそうにないとみんなが思いこんでいた。唯一伸びているIT企業がもてはやされたのだ。
このころ、日本の不況は戦後初めて世界に表れたデフレであるという論文がアメリカの経済学者からでる。日本の不況はバブル崩壊の後始末はすでについており、長引く景気低迷は、1929年の世界恐慌と同じ現象が日本に起こっているからだ、というものだった。日本の経済学者はこれにすぐに反応し、ネット上で膨大な議論が展開され、それが正しいという結論が00年頃には出ていた。しかし、その結論は現在でも一般に認知されていない。
日本の景気を回復するために、大きな財政政策を投入すべきという政策も主張され、小渕政権で一旦は財政出動で景気が上向きかけたが、01年の小泉政権になって、あれほど大失敗として世界中に公認されている橋本政権の誤りを再び徹底的に押し進めるという「痛みがともなう小泉構造改革」が始まる。
マスコミでは積極財政派が抵抗勢力というレッテルを貼られて、姿を消し、国民の閉塞感を改革によって晴らすという洗脳に成功したおかしな政治家や経済学者たちがテレビに頻繁に出てくるようになった。
96年にホームページをつくる会社を興したホリエモンはこのような流れの中にいた。当時はホームページ制作に一本1000万円くらい出す企業はいくらでもあった。一本、億単位で受注できたかも知れない。インターネットやコンピュータを導入して顧客との直接取引の割合を増やし、経費を削減しようという風潮であり、流通業者を排除する中抜きという言葉が流行った。
つまり、不況で余計なカネを使いたくないという企業や国民のニーズが集中し、経費を削減するためのIT予算がドッとソフト開発やシステム開発企業に流れた。IT業界の中でバブルが再現され仕事が増え、売上を増やしたのがホリエモンたちだ。
構造改革ブームで財政赤字削減キャンペーンが展開される中、ホームページをつくるというホリエモンの本業が流行れば流行るほど、企業は経費を減らし、一部国民もインターネットで安い品物が買えるという方向を選んだ。IT企業はほんのわずか雇用を増やしたかも知れないが、それ以上に主に政府予算の伸び不足、GDP成長率の低迷で、既存の流通業者、製造業、土木建築業などは雇用を格段に減らしたのだった。すべての若者がITで飯を食おうとは思わないから、ニートやフリーターがどんどん増え、現代の若者の失業率は目を見張るばかりに拡大してしまった。
これが構造改革とIT企業の持ちつ持たれつの関係である。(この稿続く)
ライブドアについては「ホリエモンの錬金術」
http://blog.goo.ne.jp/yamane_osamu/e/d00aeb354cc4401b60aa87e8569760ad
が早くから、でたらめぶりを指摘していた。
一方で、「小泉の波立ち」
http://www005.upp.so-net.ne.jp/greentree/koizumi/main.htm
は、この程度の帳簿操作などどうってことない、もっと悪いのは小泉だ、といっている。
どちらかが間違っているのではなく、両立していると思う。
その上で、なぜ、このような事件が起こるのかだ。
ホリエモンがライブドアの前身、オン・ザ・エッジをつくったのが1996年。前年の95年がインターネット元年と呼ばれた時期で、わたしも95年暮れにはホームページをつくっていた。そのころ県内にはまだホームページは100もない頃で、ヤフーから電話がかかってきて、掲載しても良いか、許可を求めてきた時期でもある。
世の中はといえば、バブル崩壊で、価格破壊というフレーズが連日叫ばれた。円高で海外旅行が急拡大し、沖縄観光は危機的な状況となっていた。沖縄旅行より海外の方が安いし、サービスも良い、といわれた。しかし、バブル期に客室不足となっていた沖縄では、94年までに大型ホテルが続々開業したため、沖縄全体の稼働率が急激に低下し、危機を迎える。
政府の無駄遣いが連日問題となり、行政改革、金融ビッグバン、省庁再編などが実行された。公務員叩きがくり返され、不況の原因は官僚による無駄な公共投資が原因であるとされた。
日米関係ではポスト冷戦で、日米同盟はいらなくなったのではないか、という議論がある一方、湾岸戦争で日本がもたついたことから、同盟強化に向けて米国の圧力が高まった。
世の中には「日本経済に右肩上がりはあり得ない。少子・成熟社会ではこれまでのような高成長は望めず、GDP成長率はせいぜい2、3%」という迷信が広まった。政府は財政赤字を縮小するために、行・財政改革を優先し、規制緩和を打ち出し、97年、橋本政権下で累進課税を緩和、消費税を3%から5%に拡大する。銀行やゼネコンの経営が破綻し、公的資金がどんどん注入されていった。
社会には不満が充満し、閉塞感という言葉も流行った。不況が5年も続き、今後も景気は良くなりそうにないとみんなが思いこんでいた。唯一伸びているIT企業がもてはやされたのだ。
このころ、日本の不況は戦後初めて世界に表れたデフレであるという論文がアメリカの経済学者からでる。日本の不況はバブル崩壊の後始末はすでについており、長引く景気低迷は、1929年の世界恐慌と同じ現象が日本に起こっているからだ、というものだった。日本の経済学者はこれにすぐに反応し、ネット上で膨大な議論が展開され、それが正しいという結論が00年頃には出ていた。しかし、その結論は現在でも一般に認知されていない。
日本の景気を回復するために、大きな財政政策を投入すべきという政策も主張され、小渕政権で一旦は財政出動で景気が上向きかけたが、01年の小泉政権になって、あれほど大失敗として世界中に公認されている橋本政権の誤りを再び徹底的に押し進めるという「痛みがともなう小泉構造改革」が始まる。
マスコミでは積極財政派が抵抗勢力というレッテルを貼られて、姿を消し、国民の閉塞感を改革によって晴らすという洗脳に成功したおかしな政治家や経済学者たちがテレビに頻繁に出てくるようになった。
96年にホームページをつくる会社を興したホリエモンはこのような流れの中にいた。当時はホームページ制作に一本1000万円くらい出す企業はいくらでもあった。一本、億単位で受注できたかも知れない。インターネットやコンピュータを導入して顧客との直接取引の割合を増やし、経費を削減しようという風潮であり、流通業者を排除する中抜きという言葉が流行った。
つまり、不況で余計なカネを使いたくないという企業や国民のニーズが集中し、経費を削減するためのIT予算がドッとソフト開発やシステム開発企業に流れた。IT業界の中でバブルが再現され仕事が増え、売上を増やしたのがホリエモンたちだ。
構造改革ブームで財政赤字削減キャンペーンが展開される中、ホームページをつくるというホリエモンの本業が流行れば流行るほど、企業は経費を減らし、一部国民もインターネットで安い品物が買えるという方向を選んだ。IT企業はほんのわずか雇用を増やしたかも知れないが、それ以上に主に政府予算の伸び不足、GDP成長率の低迷で、既存の流通業者、製造業、土木建築業などは雇用を格段に減らしたのだった。すべての若者がITで飯を食おうとは思わないから、ニートやフリーターがどんどん増え、現代の若者の失業率は目を見張るばかりに拡大してしまった。
これが構造改革とIT企業の持ちつ持たれつの関係である。(この稿続く)
Posted by 渡久地明 at 13:06│Comments(0)
│デフレ脱却